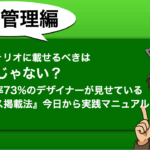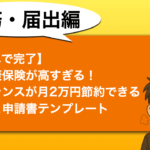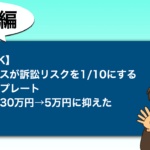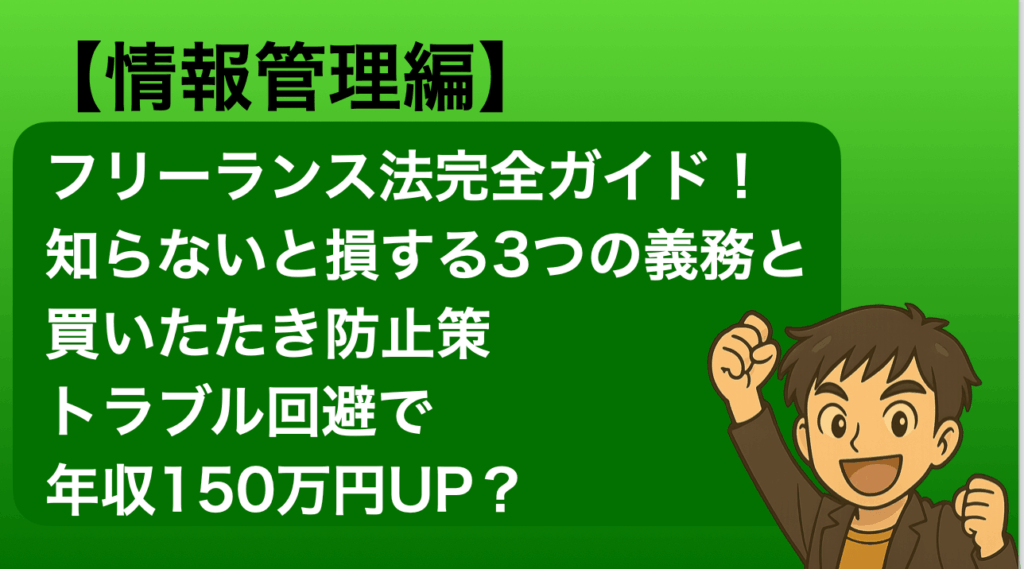
こんにちは。フリーランスひかるです。
2年前、クライアントから突然「やっぱり今回の案件は予算オーバーだから、報酬を半額にしてもらえる?」と連絡が来たときのことを今でも覚えています。納期まであと3日、すでに8割方完成していたのに、です。
あのとき私は悔しくて眠れませんでした。でも、どうしていいかわからなくて結局泣き寝入り。そんな経験、あなたも心当たりありませんか?
実は2024年11月から「フリーランス法」が施行され、フリーランスが安心して働ける環境を整備するための法律ができたんです。この法律を知らないと、本当にもったいない!
私自身、この法律の内容を深く理解してから、理不尽な要求をするクライアントとキッパリ決別できました。結果として、1年で年収が150万円もアップ。信頼できるクライアントとの長期契約も3件増えました。
✅ この記事はこんな方におすすめ
- クライアントに理不尽な要求をされて困っている
- 単価アップの交渉に自信が持てない
- 契約書の内容が曖昧で不安を感じている
- フリーランス法について詳しく知りたい
フリーランス法って何?私たちを守る盾のような存在
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(正式名称:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)、通称「フリーランス法」は、私たちフリーランスの働き方を根本から変える可能性を秘めた法律です。
なぜこの法律ができたの?
正直に言うと、フリーランスって立場が弱いんですよね。私も経験がありますが、大手企業から「これが弊社の標準条件ですから」と言われると、なかなか反論できません。
個人として業務を受けるフリーランスは、発注する側の企業などに比べ、取引において立場が弱いことが多いのが実情だったからこそ、この法律が生まれました。
私の友人のデザイナーも、「急に仕様変更されて工数が2倍になったのに、追加費用はもらえなかった」と嘆いていました。こういう理不尽な状況を防ぐのが、この法律の役割です。
フリーランス法の適用範囲
この法律で守られるのは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものつまり、私たちのような個人事業主や一人法人です。
業種に制限はありません。ライター、デザイナー、プログラマー、コンサルタント、配達員まで、幅広く適用されます。
フリーランス法で発注者に課せられる3つの義務
1. 取引条件の明示義務
これ、本当に重要です!発注事業者は、フリーランスに業務委託する際、業務内容や報酬、支払期日などの条件を文書や電子データで明示する義務があります。
以前の私は、「メールで『いい感じにお願いします』って言われて、結果的に想定の3倍の作業量になった」なんて経験がありました。でも今は違います。
「申し訳ございませんが、フリーランス法に基づき、業務内容と報酬を明文化していただけますか?」とお願いするだけで、クライアントもきちんと対応してくれます。
2. 報酬支払期限の遵守
発注事業者は、物品やサービスを受け取った日から原則60日以内に報酬を支払わなければならないという規定があります。
つい先日、新しいクライアントから「支払いは120日後」と言われました。以前なら受け入れていたかもしれませんが、今は自信を持って「法律で60日以内と定められています」と説明できます。
3. 禁止行為の遵守
フリーランス法では、発注者に対して以下のような行為を禁止しています。
- 買いたたき:相場よりも著しく低い報酬での発注
- 減額:合意した報酬を一方的に減らす行為
- 受領拒否:正当な理由なく成果物を受け取らない行為
私の知人のライターは、記事を納品したのに「思ったのと違う」という理由で受領拒否されたことがありました。でも今は、こういった行為は法律で明確に禁止されているんです。
フリーランス法と下請法の違い – どっちが私たちを守ってくれる?
よく「下請法があるからフリーランス法はいらないんじゃない?」と言われますが、実は大きな違いがあります。
適用範囲の違い
下請法は、取引の発注者の資本金が一定の金額以上になる場合に適用される法律です。しかしながら、フリーランスに取引を発注する委託事業者の多くは、資本金1,000万円以下であることが多く、実際には保護されないケースが多かったんです。
一方、フリーランス保護新法は、このような資本金要件の制限なく、フリーランスに対して取引を発注する委託事業者を規制し、フリーランスを保護するものです。
対象業務の違い
下請法では「建設業法における建設工事」や「企業が自ら用いる役務(運送、コンサルタント、営業、演奏、セラピー、物品の修理など)を他の事業者に委託する」ことは対象外です。一方、フリーランス新法は業種や業界の限定がないため建設工事も業務委託の対象になります。
私のような多種多様な案件を手がけるフリーランスにとって、フリーランス法の方がはるかに心強い存在なんです。
実際にフリーランス法を活用した体験談
ケース1:買いたたきを回避した話
3ヶ月前、ウェブサイト制作の案件で相場の半分以下の金額を提示されました。以前なら「仕事がないよりはマシ」と受けていたかもしれません。
でも今回は違いました。「フリーランス法では買いたたきが禁止されています。同様の案件の相場は○○万円ですが、いかがでしょうか?」と冷静に伝えることができました。
結果、クライアントは「そうだったんですね、すみません」と謝罪し、適正な金額で契約してくれました。この一件で、私は約30万円の損失を防ぐことができたんです。
ケース2:相談窓口の活用
先月、あるクライアントから度重なる仕様変更を要求され、精神的に追い込まれそうになりました。
そんなとき、厚生労働省の「フリーランス・トラブル110番」(電話:0120-542-330)に相談しました。専門の相談員が親身になって話を聞いてくれ、対処法をアドバイスしてもらえました。
参考URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077645.html
一人で抱え込まず、こうした相談窓口を活用することで、メンタル面でも随分楽になりました。
 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A)
Q1. フリーランス法は全てのフリーランスに適用されますか?
A:👉はい。業種や契約金額に関係なく、従業員を使用せずに業務を行う個人のフリーランスが対象です。
Q2. フリーランス法違反があった場合、どこに相談すればいいですか?
A:👉公正取引委員会や厚生労働省の相談窓口に相談できます。「フリーランス・トラブル110番」も利用できます。
Q3. フリーランスとして、この法律を根拠に報酬アップの交渉はできますか?
A:👉直接的な報酬アップの根拠にはなりませんが、適正な取引条件の明示を求めることで、結果的に条件改善につながることがあります。
Q4. フリーランス法に違反した発注者への罰則はありますか?
A:👉公正取引委員会による指導や勧告、命令などがあります。悪質な場合は罰金も課せられます。
最近では小学館、光文社、ヨドバシカメラ、島村楽器などがニュースになりましたね。
Q5. フリーランス法の施行前の契約にも適用されますか?
A:👉2024年11月1日以降に成立した契約から適用されます。既存契約は対象外ですが、更新時には適用されます。
 「フリーランスの実務」は不安がいっぱい
「フリーランスの実務」は不安がいっぱい
フリーランスの実務って、たくさんあって覚えきれない…。
フリーランスとして一人で仕事をする中で、「これ、誰にも相談できない…」と不安になる場面、ありませんか?
そんな声をもとに作られたのが、CFQ(個人事業経営士)公式参考書です。
「経営実務のスキルを持ち、信頼されるフリーランス」になるために
この参考書は、単なる制度解説ではありません。
- 届出・税務・契約・保険などの基礎知識
- リアルなケーススタディ
- その場で確認できる4択式理解テスト
といった3ステップ構成で、あなたの「なんとなく不安」を「自信」に変える実践的な教材です。
この1冊があれば、もう一人で不安にならなくていい。
あなたの「事業者としての土台」を、しっかりと支えてくれる教科書です。
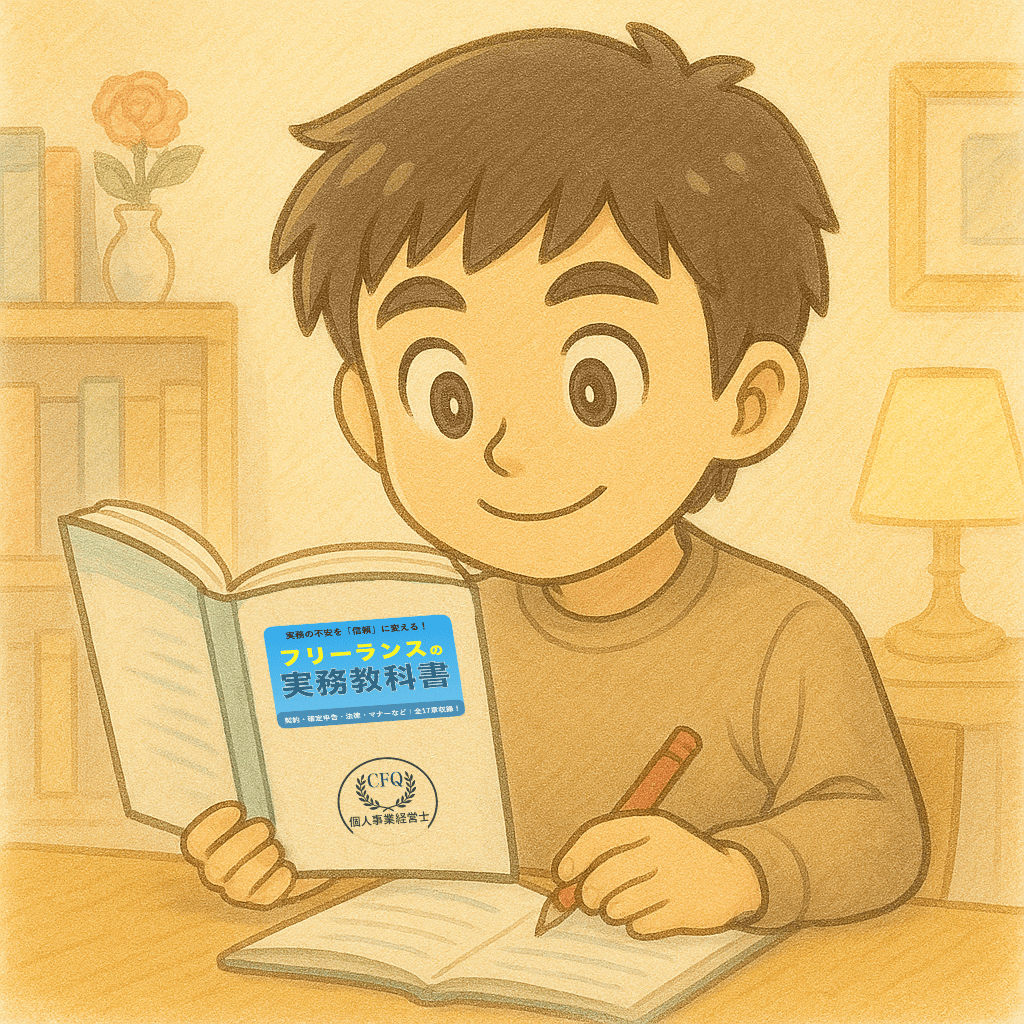
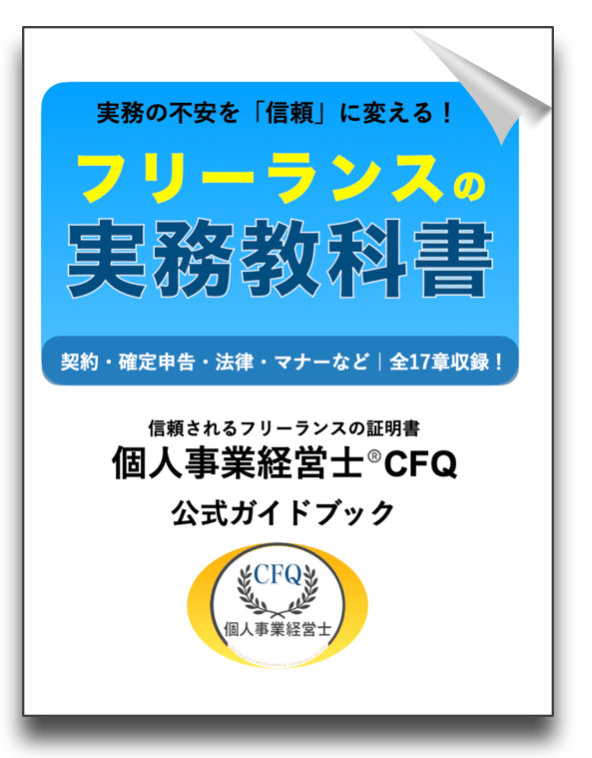
【まとめ】フリーランス法は私たちの未来を変える希望の光
フリーランス法ができて、私たちの働く環境は確実に良い方向に変わりました。でも、法律があっても私たち自身が行動しなければ、何も変わりません。
大切なのは、「自分の価値を正しく理解し、適正な対価を堂々と要求すること」です。まるで武士が刀を持つように、私たちもフリーランス法という武器を手に、自信を持って仕事に臨めるようになったんです。
最初は勇気がいるかもしれません。でも、一度適正な条件で仕事をすると、その違いに驚くはずです。クライアントからの信頼も深まり、長期的な関係が築けるようになります。
理不尽な要求に怯える日々はもう終わり。フリーランス法を味方につけて、堂々と、そして楽しく仕事をしていきましょう。あなたにはその権利があるし、その価値があるんです。
私自身、いろいろな失敗した経験があったからこそ、今は慎重に、でも自信を持って実務を進められるようになりました。
「税務が不安…」「契約が苦手…」
そんな悩みも、正しい知識を持つことで大きな武器に変わります。
不安をそのままにするのではなく、学んで備えれば、あなたの自信につながり、その自信が信頼を生むという未来が待っています。
CFQは、そんなあなたの実務力を一緒に育てていきます。

 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A)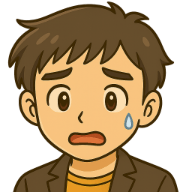 「フリーランスの実務」は不安がいっぱい
「フリーランスの実務」は不安がいっぱい