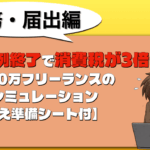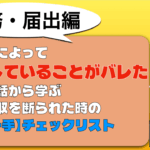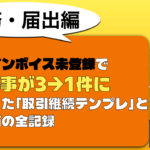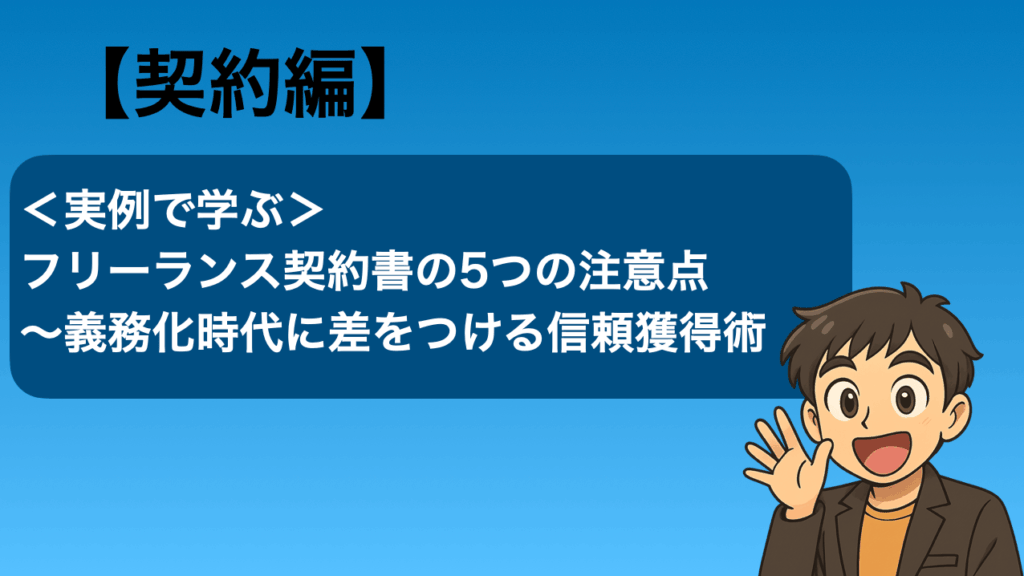
こんにちは。フリーランスひかるです。
「契約書って難しそうで、いつも後回しにしてしまう…」 「クライアントに『契約書はいいよ』と言われると、つい甘えてしまう」 「でも、本当はちゃんとした契約で単価も上げたいし、信頼されたいんだよね」
そんな風に思っているあなたの気持ち、痛いほどわかります。
実は私も、フリーランスを始めた頃は契約書を軽視していました。「お互い信頼しているから大丈夫」そう思って口約束で仕事を受けていたんです。
でも、ある日突然「想定していた成果物と違う」と言われ、3ヶ月分の報酬が支払われなかった経験があります。その時初めて「契約書がいかに大切か」を身をもって知りました。
さらに、2023年11月からフリーランス保護新法(フリーランス法)が段階的に施行され、2024年秋には契約書面の交付が義務化されました。これは私たちフリーランスにとって、実は大きなチャンスなんです。
きちんとした契約書を作れるフリーランスは、クライアントからの信頼度が格段に上がり、結果として単価アップにもつながります。
この記事では、私が実際に経験した失敗談を交えながら、フリーランスが契約書で注意すべき5つのポイントを具体的に解説していきます。
この記事はこんな方におすすめ
- クライアントに信頼されるフリーランスになりたい方
- 契約トラブルを避けて、安心して仕事に集中したい方
- 単価アップを実現したい方
- フリーランス法の義務化に適切に対応したい方
1. 報酬と支払い条件は「子どもでもわかる」レベルまで具体化する
私が一番痛い目に遭ったのが、この報酬に関する曖昧さでした。
ある企業から「Webサイトの制作をお願いしたい。報酬は50万円で、完成したら支払います」という依頼を受けました。シンプルでわかりやすいと思ったんです。
でも実際は違いました。
クライアントの「完成」と私の「完成」の認識がまったく違っていたんです。
私は「デザインとコーディングが終われば完成」だと思っていましたが、クライアントは「実際に運用開始して問題がないことを確認できたら完成」という認識でした。
結果として、納品から3ヶ月経っても「まだ完成していない」と言われ続け、報酬が支払われませんでした。
具体的な対策
報酬に関しては、以下の項目を必ず明記するようになりました。
- 総額と内訳(デザイン費30万円、コーディング費20万円など)
- 支払いタイミング(着手金50%、納品時50%など)
- 支払い方法(銀行振込、支払い手数料の負担者)
- 「完成」「検収完了」の具体的な定義
- 支払い期日(検収完了から30日以内など)
特に「検収完了」については「納品から7営業日以内に修正指示がない場合は検収完了とみなす」といった具体的な期限を設けることで、支払いの遅延を防げます。
この対策により、支払いトラブルはほぼゼロになりました。
さらに、明確な条件提示により「プロフェッショナルなフリーランス」として認識してもらえ、単価交渉もしやすくなったんです。
2. 作業範囲と修正回数は「防波堤」を築いておく
「せっかくだから、ついでにこれもお願いできる?」 「もう少しだけ修正してもらえる?」
こんな追加依頼に、断りきれずに応じてしまった経験はありませんか?
私は何度もありました。特に印象深いのは、ロゴデザインの案件です。
当初「ロゴデザイン3案、修正3回まで」という条件でスタートしたのに、気がつけば15案作成し、修正回数は20回を超えていました。
時給換算すると500円以下…。完全に赤字案件になってしまったんです。
この経験から学んだのは「作業範囲と修正回数は、自分を守る防波堤」だということです。
具体的な対策
現在は以下のような条項を必ず入れています。
【作業範囲】
・ロゴデザイン:初回3案まで
・修正:3回まで(1回の修正で複数箇所の指摘可)
・追加修正:1回につき5,000円
・作業範囲外の業務:別途見積もり
【修正の定義】
・色の変更、文字の調整など軽微な変更
・レイアウトの大幅変更は作業範囲外最初は「細かすぎるかな?」と不安でしたが、実際には「プロらしくて安心できる」と好評でした。
むしろクライアントも「何をどこまでお願いできるか」が明確になって喜ばれています。
そして何より、無限の修正地獄から解放され、本来の制作に集中できるようになりました。
3. <ここ重要!>知的財産権は「未来の自分」への投資
著作権や知的財産権について、深く考えたことはありますか?
私は恥ずかしながら、フリーランス2年目まで「納品したらクライアントのもの」という認識でした。
でも、ある日気づいたんです。自分の作品をポートフォリオに使えないことに。
印刷会社のパンフレットデザインを手がけた時のことです。
すごく良い出来で、ぜひポートフォリオに載せたかったのに、契約書には「著作権は全て発注者に帰属する」と書かれていました。
つまり、自分の作品なのに勝手に使えない状態に…。営業活動で使いたくても使えず、新規開拓に大きく影響しました。
具体的な対策
現在は知的財産権について、以下のような条項を提案しています。
【知的財産権】
・著作権:クライアントに譲渡
・著作者人格権:制作者が保持
・ポートフォリオ使用権:制作者が保持(競合他社への提示は除く)
・二次利用:別途協議「ポートフォリオ使用権」を確保することで、自分の実績として活用できます。
これは新しいクライアント獲得に直結する、いわば「未来の自分への投資」なんです。
多くのクライアントは「ポートフォリオでの使用なら問題ない」と理解を示してくれます。
むしろ「そこまで考えているなら安心」と信頼度がアップすることが多いです。
4. 機密保持と競業避止は「バランス」が命
フリーランスとして活動していると、様々な業界の案件に関わります。
でも時として「守秘義務」や「競業避止義務」が思わぬ足かせになることがあります。
私が体験したのは、ある健康食品会社のLP制作案件でした。
契約書の競業避止条項に「同業他社の業務を1年間禁止する」とあったんです。
その時は「1年くらい大丈夫」と思って署名しましたが、後に別の健康食品会社から魅力的な案件のオファーが…。でも契約違反になるため、泣く泣く断念しました。
健康食品業界は案件が多い分野だったので、結果的に大きな機会損失となってしまいました。
具体的な対策
現在は機密保持と競業避止について、以下のように調整しています。
【機密保持】
・期間:契約終了後2年間
・範囲:本業務で知り得た機密情報に限定
・例外:一般に公開されている情報、独自に取得した情報
【競業避止】
・期間:契約終了後6ヶ月間
・範囲:発注者の直接競合に限定(同業界全体ではない)
・地域制限:なし(オンライン業務のため)ポイントは「具体的かつ合理的な範囲」に留めることです。
あまりに厳しい条件は、フリーランスとしての活動を大きく制約してしまいます。
多くの場合、クライアントも「合理的な範囲であれば問題ない」と理解してくれます。
むしろ「お互いの利益を考えた提案ができる人」として評価が上がることも多いんです。
5. 契約解除と損害賠償は「お守り」として準備
「契約解除なんて考えたくない」 「うまくいくと信じて仕事をしたい」
その気持ち、とてもよくわかります。でも契約書は「保険」のようなもの。
何かあった時のための「お守り」なんです。
私が契約解除条項の大切さを実感したのは、スタートアップ企業のブランディング案件でした。
3ヶ月のプロジェクトで、すでに1ヶ月分の作業を進めていた時、クライアント側の資金調達が頓挫。
突然「プロジェクトを中止したい」と連絡がありました。
契約書に解除条項がなかったため、既に発生した費用の取り扱いや、途中まで作成したデザイン案の権利関係が曖昧に…。結局、1ヶ月分の報酬すら満額受け取ることができませんでした。
具体的な対策
現在は以下のような解除条項を設けています。
【契約解除】
・発注者都合の解除:既発生費用の100%+残作業分の30%を支払い
・受注者都合の解除:既受領金額から既発生費用を差し引いて返金
・双方合意の解除:既発生費用を基準に協議
【損害賠償】
・故意・重過失による損害:実損の範囲内
・軽過失による損害:契約金額を上限とする
・間接損害:原則として責任を負わない解除条項があることで「万が一の時も安心」という心理的余裕が生まれます。
そして結果的に、より良い関係でプロジェクトを進められることが多いんです。
あなたが「今すぐ取り組むべきこと」を体系的に解説
ここまでの内容を踏まえて、あなたが今すぐ取り組むべきことと、そのメリットを整理してみましょう。
| アクション | やること | メリット |
|---|---|---|
| 契約書テンプレートを作成する | ・今回紹介した5つのポイントを盛り込んだテンプレートを作成 ・業務内容に応じて調整できる「ひな形」として活用 | ・契約書作成時間が大幅短縮(1件あたり2時間→30分) ・見落としやミスが激減 ・プロフェッショナルな印象でクライアントからの信頼度アップ |
| 過去の案件を振り返り、トラブル要因を特定する | ・支払い遅延、追加作業、認識違いなどがなかったか確認 ・今後同じトラブルを避けるための条項を検討 | ・同じ失敗の繰り返しを防止 ・リスク管理能力の向上 ・安心して業務に集中できる環境作り |
クライアントとの契約書面交付を標準化する | ・新規案件は必ず契約書を交わす ・既存クライアントにも「法改正に伴い契約書面を整備したい」と提案 | ・フリーランス法への適切な対応 ・トラブル発生時の法的保護 ・「きちんとしたフリーランス」としてのブランディング効果 |
【中長期的な取り組み】
取り組み1:単価交渉のタイミングで契約内容も見直し
- 単価アップと同時に、より詳細な契約条件を提示
- 付加価値として「安心・安全な取引」をアピール
取り組み2:業界や案件タイプ別の契約書バリエーションを蓄積
- Web制作、デザイン、ライティングなど業務別のテンプレート作成
- クライアント規模(大企業、中小企業、個人事業主)別の調整版も準備
ここまでできれば、あなたは「契約もしっかりできる信頼できるフリーランス」として認識され、自然と単価アップや継続案件の獲得につながるでしょう。
契約書に関するよくある疑問と誤解(Q&A)
Q1. 契約書を提示すると「面倒な人」だと思われませんか?
A:👉実は逆です。私の経験では「しっかりした人だ」と評価が上がることがほとんどです。特に企業クライアントは契約書があることで安心感を持ちます。「お互いのために明確にしておきましょう」という姿勢で臨めば、必ず理解してもらえます。
Q2. 小さな案件でも契約書は必要ですか?
A:👉金額の大小に関わらず、契約書は必要です。むしろ小さな案件ほど「簡単だから大丈夫」と思いがちで、トラブルになることが多いんです。5万円の案件でも50万円の案件でも、同じようにリスクは存在します。
Q3. クライアントから「いつもの条件で」と言われた場合は?
A:👉「いつもの条件」こそ、実は一番危険です。記憶は曖昧になりがちで、認識違いが起こりやすいからです。「確認のため、改めて条件を整理させてください」と提案し、必ず書面化しましょう。
Q4. 契約書の内容でクライアントと意見が分かれた場合は?
A:👉まずは「お互いにとって良い取引にしたい」という前提で話し合います。どうしても合意できない点があれば、その案件は見送ることも大切です。無理な条件で始めた案件は、後々もっと大きなトラブルになりがちです。
Q5. 法的な知識がないと契約書は作れませんか?
A:👉完璧な契約書を作る必要はありません。大切なのは「お互いの認識を明確にする」ことです。基本的なテンプレートがあれば十分対応できます。複雑な案件の場合は、専門家に相談することも検討しましょう。
「フリーランスの実務」は不安がいっぱい
フリーランスの実務って、たくさんあって覚えきれない…。
フリーランスとして一人で仕事をする中で、「これ、誰にも相談できない…」と不安になる場面、ありませんか?
そんな声をもとに作られたのが、CFQ(個人事業経営士)公式参考書です。
「経営実務のスキルを持ち、信頼されるフリーランス」になるために
この参考書は、単なる制度解説ではありません。
- 届出・税務・契約・保険などの基礎知識
- リアルなケーススタディ
- その場で確認できる4択式理解テスト
といった3ステップ構成で、あなたの「なんとなく不安」を「自信」に変える実践的な教材です。
この1冊があれば、もう一人で不安にならなくていい。
あなたの「事業者としての土台」を、しっかりと支えてくれる教科書です。
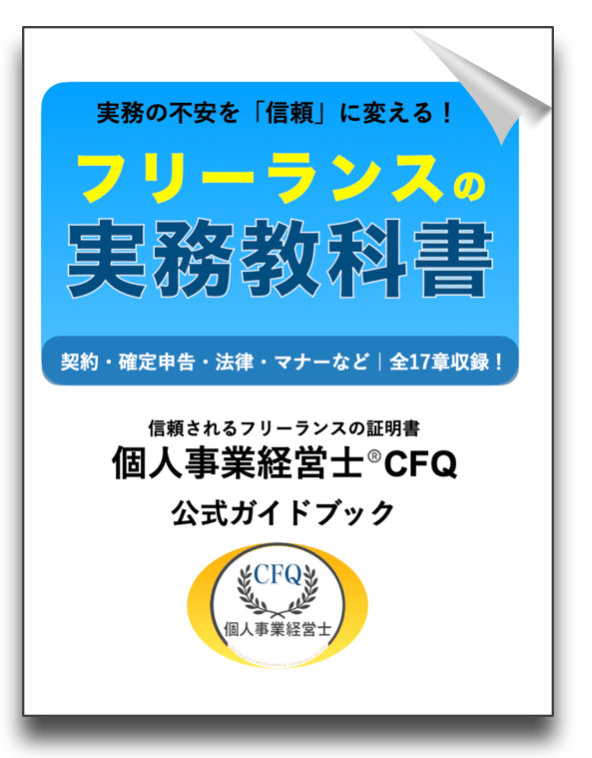
まとめ:契約書としっかり向き合う
契約書と向き合うのは、確かに面倒に感じるかもしれません。
「今までうまくいってるから大丈夫」 「お互い信頼しているから必要ない」 「難しそうでよくわからない」
そんな風に思う気持ちも、とてもよくわかります。
でも、もし今この記事を読んでいるあなたが「もっとクライアントに信頼されたい」「単価を上げたい」「安心して仕事がしたい」と思っているなら、契約書はあなたの強い味方になってくれます。
私自身、契約書をしっかり作るようになってから、明らかに仕事の質が変わりました。トラブルが減り、クライアントからの信頼が増し、結果として単価も上がりました。
何より「安心して仕事に集中できる」という精神的なメリットが一番大きかったかもしれません。
契約書は難しい法律文書ではありません。あなたとクライアントが「同じゴールに向かって歩くための地図」なんです。
船出する前に海図を確認するように、プロジェクトを始める前に契約書で道筋を確認する。それだけのことです。
あなたの未来は、今日のあなたの選択で決まります。
一歩ずつ、着実に、信頼されるフリーランスへの道を歩んでいきましょう。きっと半年後、1年後の自分が「あの時、契約書に向き合っておいて良かった」と感謝する日が来るはずです。
私自身、いろいろな失敗した経験があったからこそ、今は慎重に、でも自信を持って実務を進められるようになりました。
「税務が不安…」「契約が苦手…」
そんな悩みも、正しい知識を持つことで大きな武器に変わります。
不安をそのままにするのではなく、学んで備えれば、あなたの自信につながり、その自信が信頼を生むという未来が待っています。
CFQは、そんなあなたの実務力を一緒に育てていきます。