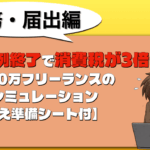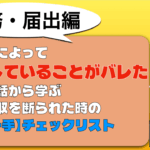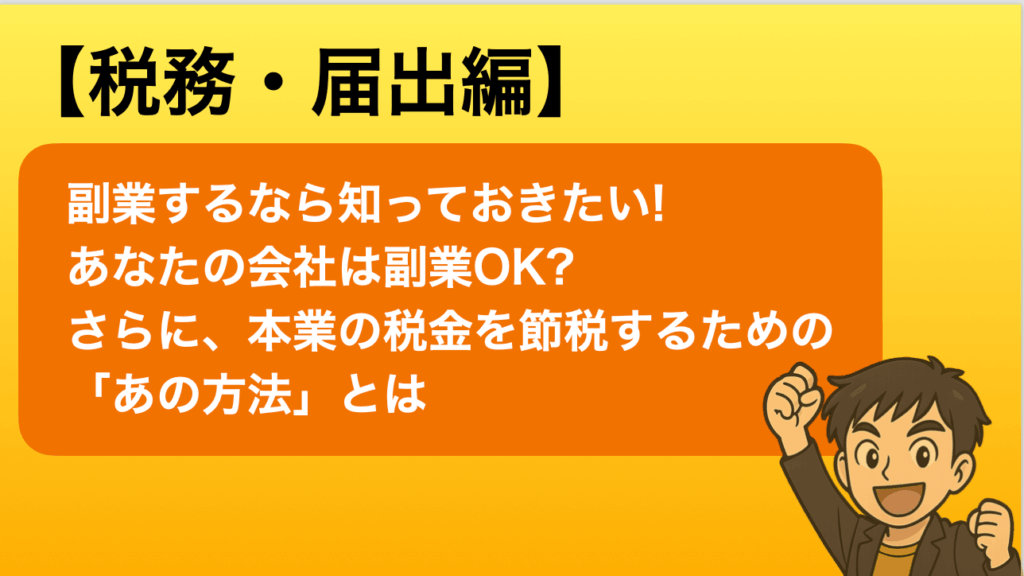
こんにちは。フリーランスひかるです。
最近、クライアント先のオフィスで打ち合わせをしていたとき、隣の席から聞こえてきた会話が妙に気になりました。「副業してるの、会社にバレたらどうしよう」という不安げな声。私も数年前、まったく同じことを思っていたんです。フリーランスとして独立する前、会社員時代に副業を始めたときの、あの胸がざわざわする感覚を今でも覚えています。
副業をしている人、これから始めようとしている人にとって、「会社にバレるのか」「税金はどうなるのか」という問題は、誰もが一度は直面する壁ですよね。実は、この問題を正しく理解しているかどうかで、あなたのキャリアの選択肢は大きく変わってきます。
✅ この記事はこんな方におすすめ
- 副業を始めたいけれど、会社にバレないか不安な方
- すでに副業しているが、確定申告や税金の仕組みがよくわからない方
- フリーランスとして独立を考えているが、税務面が心配な方
- クライアントとの契約や信頼関係を築きたいと考えている方
- 本業と副業、両方の収入を賢く管理したい方
副業が会社にバレる本当の理由
私が会社員時代に副業を始めたのは、今から5年前のことでした。当時はデザインの仕事を週末だけ受けていて、月に5万円ほどの収入がありました。「これくらいなら大丈夫だろう」と思っていたんです。でも、ある日人事部から呼び出しを受けました。
「住民税の金額が、給与に対して高すぎるんだけど」
その瞬間、頭が真っ白になりました。副業がバレる理由は、SNSでの発信でも、同僚の密告でもなく、「住民税」だったんです。
住民税の仕組みを知らないと危険
多くの人が誤解していますが、副業が会社にバレる最大の原因は「住民税の通知」です。会社員の場合、住民税は給与から天引きされる「特別徴収」という方式が一般的。この金額は、前年の所得に基づいて計算されます。
副業で20万円以上の所得がある場合、確定申告が必要になります。そして、確定申告をすると、本業と副業を合わせた所得をもとに住民税が計算され、その通知が会社に届くんです。つまり、給与に見合わない高い住民税額が会社に知られてしまうわけです。
実際に、国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、副業をしている給与所得者は年々増加しており、2022年時点で約10%を超えています。それに伴い、住民税経由で副業が発覚するケースも増えているんですね。
「副業OK」でも油断は禁物
私が当時勤めていた会社は、就業規則では「副業禁止」とは明記されていませんでした。でも、暗黙の了解として「副業はしないもの」という空気があったんです。人事部との面談では「今後も続けるなら、正式に届け出を出してほしい」と言われました。
最近では、政府の働き方改革の推進もあり、副業を認める企業が増えています。リクルートワークス研究所の調査では、2023年時点で約70%の企業が副業を容認または条件付きで認めています。
でも、「副業OK」の会社でも注意が必要です。例えば、以下のようなケースは問題になることがあります。
- 競合他社での副業
- 本業に支障が出るほどの長時間労働
- 会社の機密情報を使った副業
- 会社の名前や信用を利用した営業活動
実際に、2021年には大手IT企業の社員が、競合企業で副業をしていたことが発覚し、懲戒処分を受けた事例が報道されました。副業OKだからといって、何でもしていいわけではないんです。
確定申告しないと「バレる」だけじゃ済まない
副業を始めた最初の年、私は確定申告をしませんでした。「20万円ちょっとだし、バレないだろう」という甘い考えでした。でも、これが大きな間違いだったんです。
税務署は意外と見ている
フリーランスになってから知ったのですが、税務署は私たちが思っている以上に情報を持っています。クライアントが支払調書を提出していれば、あなたに支払われた金額は税務署に筒抜けです。
支払調書とは、企業が個人に報酬を支払った場合に税務署に提出する書類のこと。年間5万円以上の支払いがあれば、提出義務が生じることがあります。つまり、あなたが確定申告しなくても、税務署はあなたの収入を把握しているかもしれないんです。
無申告のペナルティは想像以上
確定申告をしないと、どんなリスクがあるのでしょうか。私の知人は、3年間無申告だったことが発覚し、以下のペナルティを受けました。
- 無申告加算税:本来の税額の15〜20%
- 延滞税:年利最大14.6%
- 重加算税:悪質と判断されると最大40%
知人のケースでは、本来30万円程度の税金だったものが、加算税や延滞税を含めて50万円以上になってしまいました。さらに、その間の精神的なストレスは計り知れません。毎日「いつバレるんだろう」という不安を抱えながら生活するのは、本当につらいものです。
国税庁の発表によると、2022年度の個人に対する税務調査では、約80%のケースで申告漏れが指摘されています。「バレないだろう」という考えは、本当に危険なんです。
副業の税金を賢く管理する「あの方法」
ここまで読んで、「じゃあ、どうすればいいの?」と思いましたよね。実は、副業の税金を適切に管理しながら、本業の会社に知られずに済む方法があるんです。それが「普通徴収」という仕組みです。
住民税を自分で納める選択肢
確定申告書には、住民税の徴収方法を選択する欄があります。ここで「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業分の住民税は自宅に納付書が届き、自分で納めることができます。本業の給与から天引きされる住民税は、本業の給与分だけになるため、会社に副業の収入が知られにくくなるんです。
私はこの方法を知ってから、確定申告の際に必ず「自分で納付」を選択するようにしています。ただし、自治体によっては対応が異なる場合もあるので、事前に市区町村の税務課に確認することをおすすめします。
実際に、東京都主税局のウェブサイトでも、副業の住民税を普通徴収にする方法について詳しく説明されています。 参考:東京都主税局「個人住民税」https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html
経費をしっかり計上する
副業の所得は「収入−経費」で計算されます。つまり、経費をきちんと計上することで、課税される所得を減らすことができるんです。
私が会社員時代に副業していたときは、以下のような経費を計上していました。
- パソコンやソフトウェアの購入費用
- 打ち合わせのためのカフェ代や交通費
- 仕事用の書籍や教材費
- インターネット通信費(按分)
- 仕事用の文具や消耗品
例えば、月5万円の副業収入があっても、経費が月1万円あれば、所得は月4万円。年間で計算すると、所得が60万円から48万円に減ります。この12万円の差は、税金に換算すると数万円の節税になるんです。
会計ソフトで管理を楽に
最初は手書きの帳簿をつけていましたが、あまりにも大変で、途中で挫折しそうになりました。そこで導入したのが、クラウド会計ソフトです。
私が使っているのは「freee」というサービスです。銀行口座やクレジットカードと連携できるので、収入や経費が自動で記録されます。確定申告書類も自動で作成してくれるので、税務の知識がなくても安心です。
freee公式サイト:https://www.freee.co.jp/
他にも「マネーフォワード クラウド確定申告」や「やよいの青色申告オンライン」など、複数のサービスがあります。月額1,000円程度から利用できるので、副業を始めたばかりの方にもおすすめです。
フリーランスになるなら知っておきたい節税の基本
副業から始めて、いずれフリーランスとして独立することを考えている方も多いでしょう。私も5年前はそうでした。フリーランスになると、税金の管理は完全に自分の責任になります。でも、その分、節税のチャンスも増えるんです。
青色申告で最大65万円控除
フリーランスになったら、まず検討したいのが「青色申告」です。青色申告とは、一定の帳簿をつけることで税制上の優遇を受けられる制度のこと。最大65万円の特別控除を受けられるので、大きな節税になります。
私は独立した年から青色申告を選択しました。例えば、年間の所得が300万円の場合、青色申告特別控除65万円を引くと、課税所得は235万円になります。税率を20%とすると、約13万円の節税になる計算です。
青色申告を選ぶには、事業開始から2ヶ月以内(または3月15日まで)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。国税庁のウェブサイトから書式をダウンロードできます。 参考:国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
小規模企業共済で退職金を積み立てる
フリーランスには退職金がありません。でも、「小規模企業共済」という制度を使えば、自分で退職金を積み立てながら節税もできるんです。
この制度は、月額1,000円から70,000円まで自由に積み立てができます。そして、掛金の全額が所得控除の対象になります。例えば、月3万円を積み立てた場合、年間36万円が所得から控除されるので、税率20%なら約7.2万円の節税になります。
私は現在、月2万円を積み立てています。将来への備えをしながら、今の税金も減らせるので、一石二鳥だと感じています。
小規模企業共済は中小機構が運営しており、全国の商工会議所などで加入できます。 参考:中小機構「小規模企業共済」https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
iDeCoでさらに節税
さらに節税効果を高めたいなら、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」も検討する価値があります。iDeCoも掛金が全額所得控除の対象になり、フリーランスの場合、月額最大68,000円まで積み立てられます。
私の知人のフリーランスエンジニアは、小規模企業共済とiDeCoを併用して、年間100万円以上を所得控除しています。所得税と住民税を合わせると、年間30万円近い節税になっているそうです。
税理士に相談する選択肢
税金のことは複雑で、自分だけで完璧に管理するのは難しいものです。私も独立2年目から、税理士さんに相談するようになりました。
税理士報酬は年間10〜30万円程度かかりますが、適切な節税アドバイスをもらえるので、結果的にプラスになることが多いです。特に、経費の範囲や青色申告の細かいルール、将来的な法人化のタイミングなど、プロの視点でアドバイスをもらえるのは心強いものです。
税理士を探すなら、「税理士ドットコム」などの紹介サービスが便利です。複数の税理士から見積もりを取れるので、自分に合った方を見つけやすくなります。 参考:税理士ドットコム https://www.zeiri4.com/
 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A)
Q1. フリーランスになる前の副業収入、20万円以下なら申告不要ですか?
A:👉「20万円以下なら申告しなくていい」というのは、よくある誤解です。正確には、給与所得者(会社員)が副業で得た所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。つまり完全に申告不要というわけではありません。また、この「20万円」は収入ではなく「所得」(収入−経費)なので注意しましょう。
Q2. フリーランスとして独立後、会社員時代の副業収入も申告すべきですか?
A:👉はい、必要です。独立した年の1月1日から12月31日までのすべての収入を申告します。会社員時代の給与と、独立後の事業所得の両方を含めて確定申告を行ってください。会社からもらう源泉徴収票も必要になります。
Q3. フリーランスが複数のクライアントと仕事する場合、それぞれ別の収入として申告しますか?
A:👉いいえ、基本的にはすべて合算して「事業所得」として申告します。ただし、帳簿にはクライアントごとに収入を記録しておくと、管理がしやすくなります。万が一税務調査があった場合にも、きちんと説明できるようにしておきましょう。
Q4. フリーランスが副業で法人から報酬を受け取る場合、源泉徴収されますか?
A:👉クライアントによります。契約時に確認しましょう。法人が個人に報酬を支払う場合、10.21%(100万円超の部分は20.42%)の源泉所得税が差し引かれます。ただし、これは前払いの税金なので、確定申告で精算できます。源泉徴収票または支払調書を保管しておきましょう。
Q5. フリーランスの副業収入、家族に知られずに管理できますか?
A:👉確定申告書は本人しか見られませんが、住民税の通知書は世帯主に届くこともあります。また、銀行口座の入金記録などから家族に知られる可能性はあります。完全に秘密にするのは難しいですが、きちんと管理していれば、堂々と説明できるはずです。むしろ、家族の理解を得ながら活動する方が、長期的には良い結果につながりますよ。
 そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!
そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!
フリーランスの実務や疑問を解決するためには、「フリーランスの実務教科書」をお勧めします。
この参考書は、単なる理論の解説ではありません。
- 届出・税務・契約・保険などの基礎知識
- 実際に起こる事例でケーススタディ
- 4択式テストで理解度をチェック
といった3ステップ構成で、あなたの不安を「自信」に変える実践的な教材です。
もう一人で不安にならなくていい。
あなたの「フリーランスとしての信用」をしっかり支えてくれる教科書です。
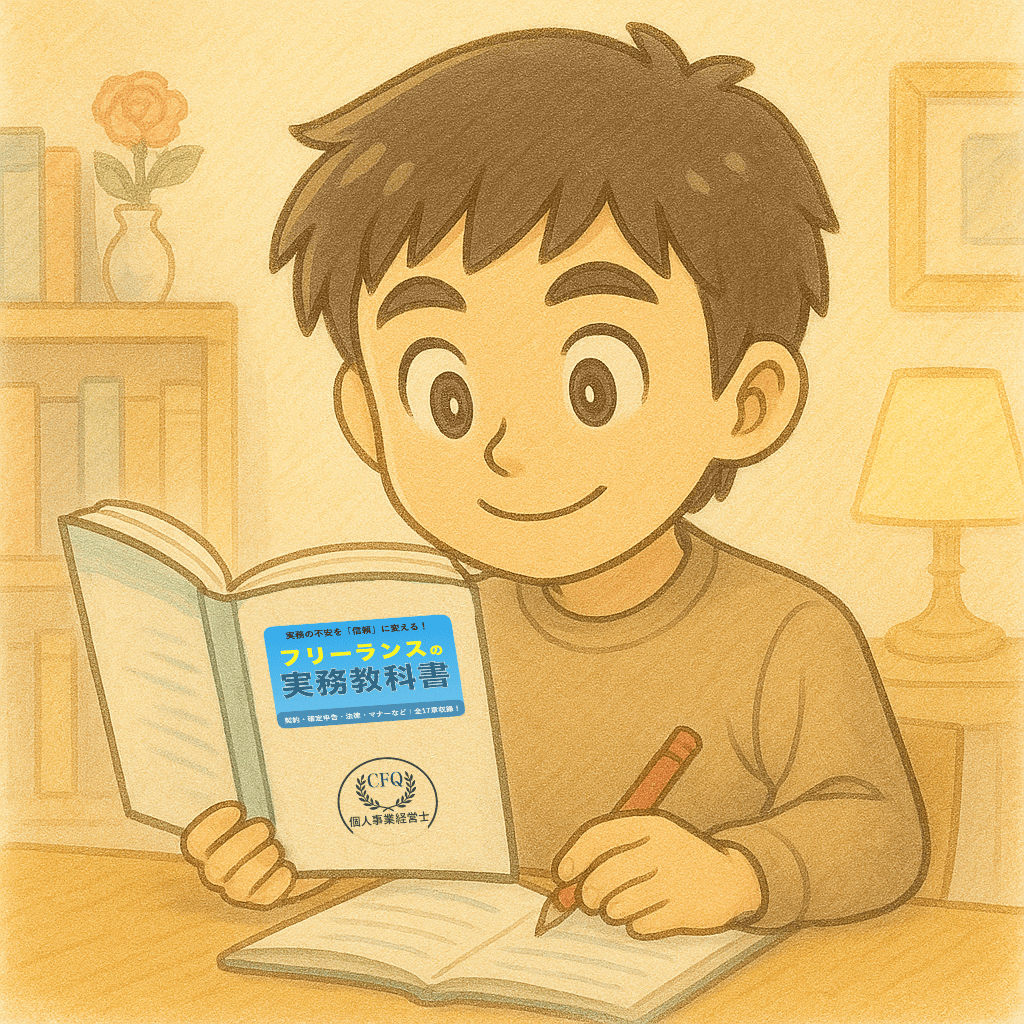
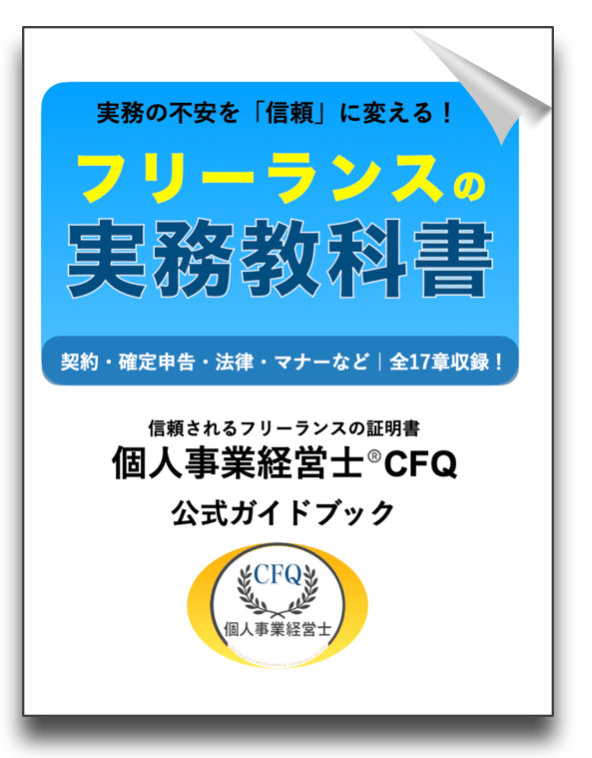
【まとめ】副業は隠れずにやろう!
副業や税金の話って、最初はすごく難しく感じますよね。私も会社員時代、確定申告の書類を前にして、何度も頭を抱えました。「これで本当に合ってるのかな」「会社にバレたらどうしよう」という不安は、夜も眠れないほどでした。
でも、今振り返ると、あの不安があったからこそ、税金のことをしっかり学ぶきっかけになったんです。知識を身につけることで、不安は自信に変わります。副業も、税金も、怖がるものではなく、うまく付き合っていくものなんだと気づきました。
大切なのは、完璧を目指すことではありません。少しずつ、できることから始めることです。まずは確定申告の仕組みを理解する。住民税を普通徴収にする。経費をきちんと記録する。会計ソフトを導入してみる。一つひとつは小さな一歩でも、積み重ねることで、大きな安心につながります。
あなたの副業や独立への挑戦は、新しい可能性への扉です。税金の知識は、その扉を安全に開くための鍵のようなもの。正しい知識を持っていれば、自信を持って前に進めます。
迷いや不安を感じるのは、真剣に向き合っている証拠です。その真剣さを大切にしながら、一歩ずつ進んでいきましょう。あなたにはその力があります。そして、その選択をする勇気も。
私自身、いろいろな失敗した経験があったからこそ、今は慎重に、でも自信を持って実務を進められるようになりました。
「税務が不安…」「契約が苦手…」
そんな悩みも、正しい知識を持つことで大きな武器に変わります。
不安をそのままにするのではなく、学んで備えれば、あなたの自信につながり、その自信が信頼を生むという未来が待っています。
フリーランスの新しい資格「CFQ」は、そんなあなたの実務力を一緒に育てていきます。

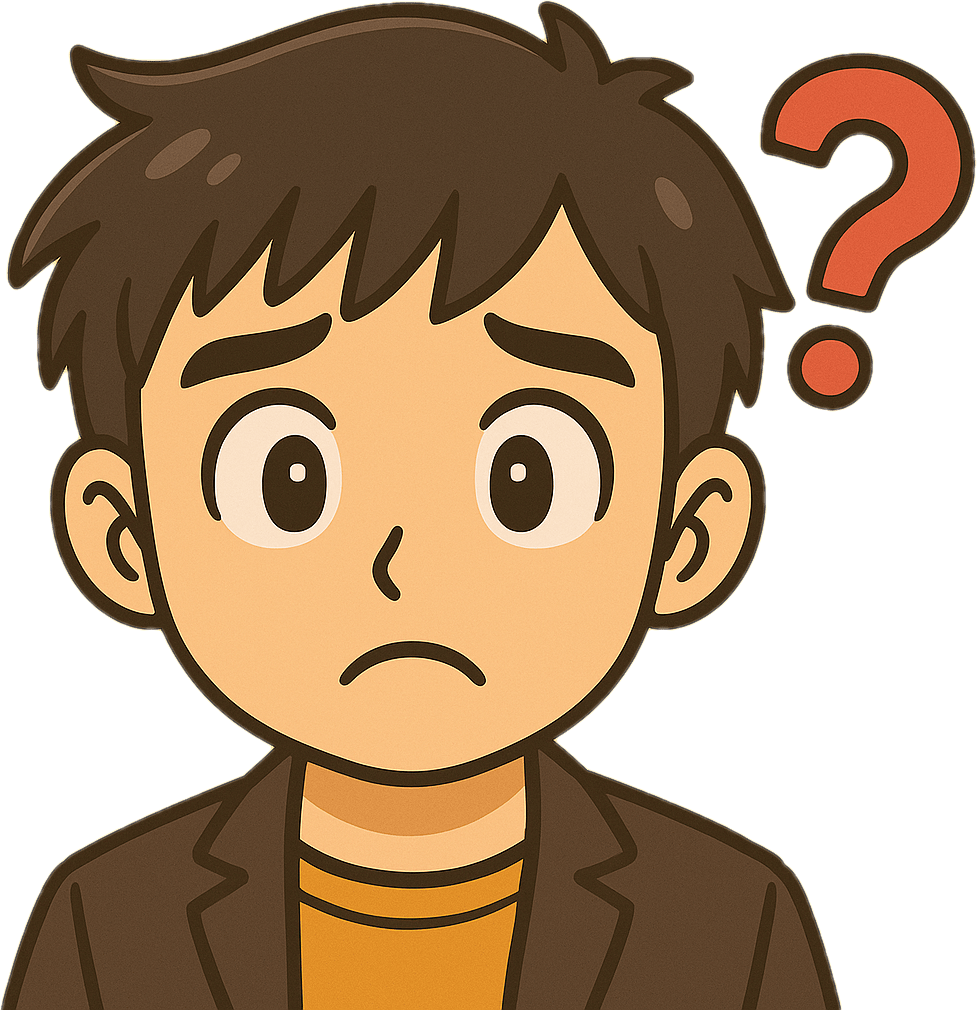 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A) そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!
そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!