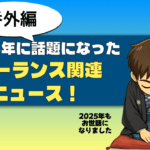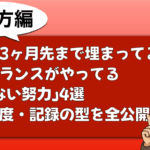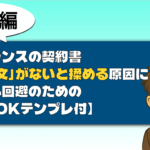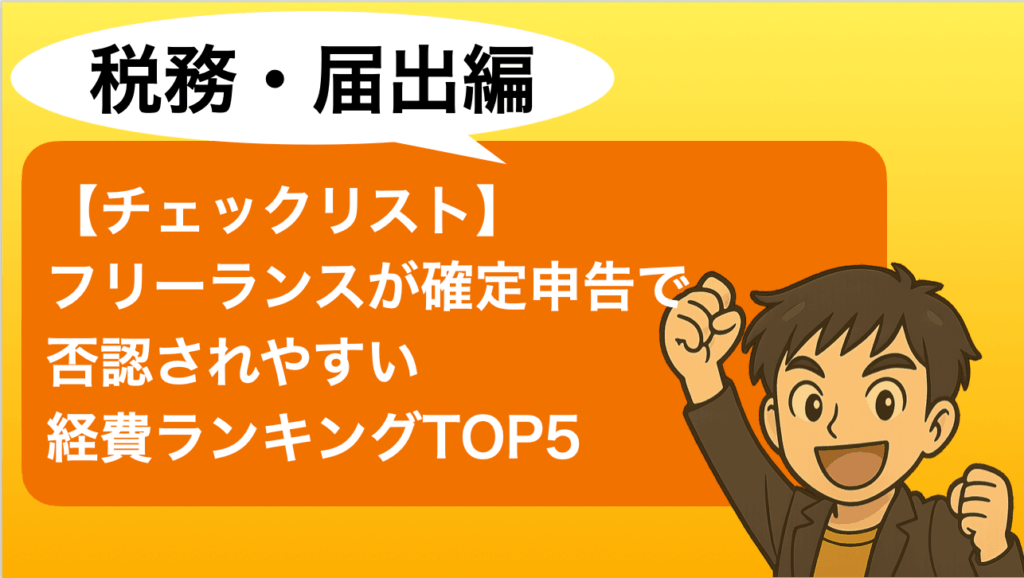
こんにちは。フリーランスひかるです。
確定申告の時期が近づくと、毎年思い出すんです。3年前の冬、税務署から届いた1通の封筒を開けた瞬間の、あの嫌な汗を。「修正申告のお願い」という文字が目に飛び込んできて、手が震えました。
自分では「これは経費だ」と信じて計上していたものが、税務署からは「それは認められません」と否認されたんです。
追徴課税の金額を見て、その晩は眠れませんでした。
フリーランスにとって、経費の計上は収入を守る大切な権利です。でも、その線引きを間違えると、後から痛い目に遭う。私のように、確定申告が終わって安心していたところに、突然の修正申告通知が届くこともあるんです。
「これって経費になるのかな?」と迷いながらも、なんとなく計上してしまう。その判断が、後々大きなトラブルを招くことがあります。
今日は、私の失敗談も含めて、フリーランスが確定申告で否認されやすい経費をランキング形式でお伝えします。
このチェックリストを見て、あなたの経費計上を今一度見直してみてください。
✅ この記事はこんな方におすすめ
- 確定申告で「これって経費になるのかな?」と迷ったことがある方
- 税務調査や修正申告の通知が怖いと感じている方
- 経費として計上できる範囲を正しく知りたい方
- 過去の申告内容に不安を感じている方
- 節税したいけど、グレーゾーンは避けたい方
第1位:自宅の家賃・光熱費(按分が曖昧なケース)
「家で仕事してるんだから、家賃は全部経費でしょ?」
フリーランスになりたての頃、私は本気でそう思っていました。1LKのアパートで、リビングの一角に小さなデスクを置いて仕事をしていた私は、家賃6万円のうち、半分の3万円を経費として計上していたんです。「まあ、半分くらい仕事してるし」という、なんとも曖昧な理由で。
税務調査が入ったとき、調査官は私の部屋を見渡して、こう言いました。「この部屋のどこが事業専用スペースですか?」寝室とリビングが一体になった部屋で、デスクの横にはベッドがあり、テレビもある。完全に生活空間でした。
按分の基準が曖昧だと、経費として認められないケースが非常に多いんです。国税庁の統計によると、自宅兼事務所の経費否認は、個人事業主への指摘事項の中で常に上位にランクインしています。
否認されやすいパターン
自宅の一角で仕事をしているのに、家賃の50%以上を計上している場合、まず疑われます。特に、明確な区切りがない部屋で、デスクとベッドが同じ空間にある場合は要注意です。「仕事の時間が長いから」という理由だけでは、按分の根拠として弱いんです。
光熱費も同じです。私は当時、電気代の70%を経費にしていました。「夜中まで仕事してるし、エアコンもずっとつけてるから」という理由でしたが、調査官には「プライベートの時間も同じ部屋で過ごしていますよね?」と指摘され、言葉に詰まりました。
正しい計上方法
按分の基準は「面積」か「時間」で明確に示す必要があります。例えば、30平米のワンルームで、6畳(約10平米)を事業専用スペースとして使っているなら、10÷30=約33%が適正な按分率です。
時間で計算する場合は、1日24時間のうち、実際に事業で使用している時間を記録します。例えば、1日8時間仕事をしているなら、8÷24=約33%となります。ただし、この方法を使う場合は、きちんと作業時間の記録を残しておくことが重要です。
ある税理士さんは「間取り図に事業スペースを色分けして保管しておくといい」とアドバイスしてくれました。視覚的に説明できる資料があると、税務調査でも説得力が増すそうです。
第2位:飲食費(会議費・接待交際費との線引き)
「クライアントと会ったから、これは接待交際費だよね」
そう思って、居酒屋での飲み会を全額経費計上していた時期がありました。でも、後から考えると、その飲み会の半分以上は、仕事の話なんてほとんどしていなかったんです。ただの友達との飲み会に、たまたまフリーランス仲間がいただけ。
税務署が特に厳しくチェックするのが、この飲食費です。2023年の国税庁の発表によると、個人事業主への税務調査で指摘される項目の約30%が交際費関連だというデータもあります。
否認されやすいパターン
特に多いのが「家族との食事を会議費として計上するケース」です。私の知人のデザイナーは、妻と一緒に行ったレストランでの食事を「打ち合わせ」として経費にしていました。でも、その妻は全くデザインとは関係のない仕事をしていて、しかも領収書には「ディナーコース 2名様」としか書かれていなかった。当然、否認されました。
深夜の飲食やバーでの高額な支出も、要注意です。「夜遅くまで打ち合わせをしていた」と主張しても、その時間帯に本当に仕事の話をする必要があったのか、合理的な説明ができないと認められません。
正しい計上方法
飲食費を経費にするなら、5W1Hを明確にすることが絶対条件です。領収書の裏に、いつ(When)、どこで(Where)、誰と(Who)、何のために(Why)、どんな内容の(What)、どのように(How)会ったのかをメモしておきましょう。
例えば、こんな感じです。「2025年10月15日、渋谷のカフェにて、○○株式会社の田中様とウェブサイトリニューアルの提案について打ち合わせ。見積書を提示し、次回のスケジュールを確認」
私は今、会議の後に必ずスマホでメモを残すようにしています。できれば、その場で打ち合わせ内容を簡単に議事録としてまとめ、相手にメールで送る。そうすることで、後から「確かに仕事の話をした」という証拠が残ります。
また、1人での食事は原則として経費になりません。「仕事の合間の食事だから」という理由では認められないので、注意してください。
第3位:スーツ・洋服代(業務用との区別が不明確)
「クライアントに会うときはスーツを着るんだから、これは作業着みたいなものでしょ?」
フリーランスになって最初の確定申告で、私はスーツ3着とワイシャツ数枚、合計15万円分を経費として計上しました。でも、そのスーツは、友人の結婚式にも着ていたし、プライベートの食事にも着ていた。完全に普段着だったんです。
税務調査で指摘されたとき、調査官はこう言いました。「このスーツ、今日も着ていらっしゃいますよね? プライベートでも使える服は、経費として認められません」
否認されやすいパターン
一般的なビジネススーツや、普段着としても使えるような服は、ほぼ100%否認されます。「仕事で着ている」というだけでは不十分で、「仕事でしか着られない」ことを証明する必要があるんです。
ある税理士さんが教えてくれた事例では、高級ブランドのスーツを「クライアントに会うときのイメージアップのため」として経費計上しようとした人がいたそうです。でも、そのスーツは休日のデートにも着用可能なデザインで、当然否認されました。
正しい計上方法(例外ケース)
衣服代が経費として認められるのは、非常に限られたケースです。例えば、YouTuberやインフルエンサーが動画撮影専用の衣装を購入する場合、舞台衣装のように明らかに業務専用とわかるものなら認められることがあります。
建設業や工場勤務なら作業着、警備員なら制服、料理人ならコック服。これらは「業務専用」と判断されやすいです。でも、フリーランスのデザイナーやエンジニア、ライターといった職種では、普通のスーツや私服を経費にするのは難しいと考えた方がいいでしょう。
私の知人のウェディングプランナーは、式場での打ち合わせ専用にドレスコードに合った服を購入し、それを経費として計上しました。ただし、その服は派手すぎて普段着られないデザインで、購入時のレシートと一緒に「業務専用」と明記したメモを保管していたそうです。そこまで明確にしておけば、認められる可能性は高まります。
でも正直、グレーゾーンです。迷うくらいなら、経費にしない方が安全だと私は思います。
第4位:車両費・ガソリン代(プライベート使用との区別)
「車で取材に行ったから、この1ヶ月のガソリン代は全部経費だ」
そう思って計上していた時期がありました。でも実際には、その車で週末に家族とドライブに行ったり、スーパーに買い物に行ったりもしていたんです。仕事とプライベート、完全に混ざっていました。
車両費やガソリン代は、自宅の家賃と同じく、按分が必要な経費です。でも、多くのフリーランスがここを曖昧にしてしまい、結果として否認されています。
否認されやすいパターン
特に多いのが「車の購入費用を全額経費にするケース」です。私の知人のカメラマンは、200万円の車を購入し、全額を減価償却で経費計上しようとしました。でも、その車は週末に家族を乗せて出かけたり、プライベートでも頻繁に使っていた。税務調査で指摘され、按分を求められました。
ガソリン代も同じです。「毎月1万円分給油してるから、全部経費」というのは通りません。走行距離の記録を付けていないと、事業用とプライベート用の区別ができず、否認されるリスクが高まります。
正しい計上方法
車両費を経費にするなら、走行記録が必須です。いつ、どこへ、何のために車を使ったのか、走行距離はどれくらいだったのか。これを記録しておかないと、按分の根拠が示せません。
私は今、Googleマップのタイムライン機能を使って移動記録を残しています。スマホアプリの中には、走行距離を自動で記録してくれる便利なツールもあります。例えば「MileIQ」や「Mileage Tracker」といったアプリは、GPSを使って自動で走行記録を付けてくれるので、手間が省けます。
按分の計算方法は、1ヶ月の総走行距離のうち、事業で使用した距離の割合で算出します。例えば、総走行距離が500kmで、そのうち事業用が200kmなら、200÷500=40%が事業用の按分率です。ガソリン代や車検代、保険料なども、この按分率で経費計上します。
ある税理士さんは「1年間の走行記録をエクセルにまとめて、税務署に提出できるようにしておくと安心」とアドバイスしてくれました。面倒に感じるかもしれませんが、後々のトラブルを避けるためには必要な手間です。
第5位:旅行・レジャー費(視察・研修との区別)
「この旅行は完全に視察目的だから、全額経費でしょ」
フリーランスになって2年目の夏、私は沖縄に3泊4日の旅行に行きました。目的は「リゾートホテルのウェブサイトデザインのリサーチ」。確かに、ホテルを何軒か見て回り、写真も撮りました。でも、ビーチで泳いだり、観光地を巡ったり、完全に観光も楽しんでいたんです。
それでも私は、航空券代、ホテル代、食事代、すべてを「視察費」として経費計上しました。当時は「仕事に関係あるんだから問題ない」と思っていました。でも、税務調査でこう聞かれたんです。「この4日間で、実際に仕事をしていた時間はどれくらいですか? 証拠はありますか?」
答えられませんでした。
否認されやすいパターン
旅行やレジャーを「視察」「研修」として経費にするケースは、税務署が最も疑いの目を向ける項目の一つです。特に、家族同伴の旅行や、観光地への旅行は、ほぼ確実にチェックされます。
2022年に話題になったニュースで、あるインフルエンサーが「海外旅行を全額経費にして税務調査を受けた」という事例がありました。その人は「SNSのネタ探しのため」と主張しましたが、実際には観光をメインに楽しんでいたことが発覚し、追徴課税を受けました(出典:国税庁公表資料より)。
正しい計上方法(例外ケース)
旅行費を経費にするには、明確な業務目的と証拠が必要です。例えば、セミナーや展示会への参加、取材、クライアントとの商談など、具体的な業務内容を示せる場合のみ認められます。
その場合でも、旅行全体の日程のうち、実際に業務に充てた時間の割合で按分する必要があります。3泊4日の旅行で、実際にセミナーに参加したのが1日だけなら、費用の1/4程度しか経費として認められません。
証拠として残しておくべきものは、セミナーの参加証明書、取材先との打ち合わせ記録、撮影した写真やメモ、現地で作成した資料などです。私の知人のライターは、取材旅行に行く際、必ず事前に取材計画書を作成し、現地で撮影した写真やインタビューメモをすべてファイリングしているそうです。
正直なところ、完全にプライベートの旅行なら、最初から経費にしない方が賢明です。無理に経費にしようとして、後から否認されるリスクを背負うより、最初から諦めた方が気持ちも楽です。
番外編:その他の注意すべき経費
ここまでランキング形式で紹介してきましたが、他にも否認されやすい経費はいくつかあります。
通信費(携帯電話代・インターネット代)
仕事とプライベートで同じスマホを使っている場合、按分が必要です。「仕事でしか使ってない」と主張しても、プライベートの電話やSNSも使っているなら、全額経費にはできません。私は通話履歴を見て、仕事関連の通話時間の割合を計算し、按分しています。
書籍・雑誌代
仕事に関係のある専門書なら経費になりますが、小説やマンガ、趣味の雑誌は基本的に認められません。ただし、ライターやデザイナーが「参考資料として購入した」と明確に説明できるなら、認められることもあります。購入時にレシートと一緒に「何の仕事のために購入したか」をメモしておくといいでしょう。
健康診断・ジム代
個人事業主の健康診断費用は、残念ながら経費にはなりません。法人の場合は福利厚生費として認められますが、個人の場合は「個人の生活費」と見なされます。ジム代も同様で、「健康管理のため」という理由では経費になりません。
明日からできること
経費の計上で失敗しないために、今日からできることを3つ紹介します。
ステップ1:経費の記録を習慣化する
レシートや領収書をもらったら、その場でスマホで写真を撮り、5W1Hをメモする習慣を付けましょう。会計アプリを使えば、レシートを撮影するだけで自動的に記録してくれます。「freee」や「マネーフォワード クラウド確定申告」といったツールは、初心者でも使いやすくておすすめです。
記録は溜め込まず、できれば週に1回、最低でも月に1回はまとめて整理する時間を作りましょう。私は毎週日曜日の夜、30分だけ経費整理の時間を取っています。溜め込むと面倒になるし、記憶も曖昧になるので、こまめに記録することが大切です。
ステップ2:按分ルールを明確にする
自宅兼事務所、車両、通信費など、按分が必要な経費については、自分なりのルールを決めておきましょう。そして、その根拠をきちんと記録しておくこと。例えば、間取り図や走行記録、通話履歴など、後から説明できる資料を残しておくと安心です。
私は按分ルールをエクセルにまとめて、毎年同じ基準で計算しています。ルールが明確だと、確定申告の時期になって慌てることもありません。
ステップ3:迷ったら専門家に相談する
「これって経費になるのかな?」と迷ったら、税理士さんに相談するのが一番です。無料相談を受け付けている税理士事務所も多いので、確定申告前に一度相談してみるといいでしょう。税務署の無料相談窓口も利用できます。
また、CFQ(フリーランス資格)の公式参考書には、経費計上の基礎知識や、よくある失敗事例が詳しく載っています。私もこの本を読んで、「ああ、こういうのはダメなんだ」と気づくことがたくさんありました。フリーランスとして長く活動していくなら、税務の基礎知識は必須です。
迷ったまま見切り発車で経費計上するより、正しい知識を身につけて、自信を持って申告できる方が、精神的にもずっと楽です。
 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A)
Q1. フリーランスが経費として計上できる上限額はあるのでしょうか?
A:👉経費に上限額はありません。ただし、収入に対して経費が異常に高いと、税務署から疑われる可能性があります。例えば、年収300万円なのに経費が250万円といった場合、本当にそれだけの経費が必要だったのか、詳しく調査されることがあります。大切なのは「上限を気にすること」ではなく、「本当に事業に必要だった経費かどうか」を自分自身で説明できることです。
Q2. フリーランスが経費の証明をする際、領収書がない場合はどうすればいいですか?
A:👉領収書がない場合でも、クレジットカードの明細や銀行の振込記録があれば、経費として認められることがあります。また、自動販売機での購入など、どうしても領収書が出ない場合は、出金伝票を自分で作成して記録を残しましょう。ただし、高額な支出については領収書がないと厳しいので、できる限り領収書をもらう習慣を付けることが大切です。
Q3. フリーランスが確定申告で経費を計上し忘れた場合、後から修正できますか?
A:👉確定申告の期限後でも、5年以内であれば「更正の請求」という手続きで経費を追加計上し、還付を受けることができます。ただし、税務署の審査が必要なので、必ずしも認められるわけではありません。逆に、経費を多く計上しすぎた場合は「修正申告」を行い、不足分の税金を納める必要があります。いずれにしても、最初から正確に申告することが一番です。
 CFQ(個人事業経営士)公式参考書で「実務力」を固める
CFQ(個人事業経営士)公式参考書で「実務力」を固める
「契約が不安…」「税務が怖い…」「トラブルが心配…」
そんな「なんとなく不安」を抱えたまま、フリーランスを続けていませんか?
CFQ(個人事業経営士)公式参考書は、まさにそんな人のために作られました。
この1冊で学べること
- 届出・税務の基礎(開業届、青色申告、インボイス制度)
- 契約・法務の実務(契約書の作り方、著作権、下請法)
- 保険・リスク管理(損害賠償、PL保険、トラブル対応)
- ケーススタディ(実例から学ぶ失敗パターン)
- 4択式テスト(理解度チェック)
単なる制度解説ではなく、「明日から使える実務知識」が詰まっています。
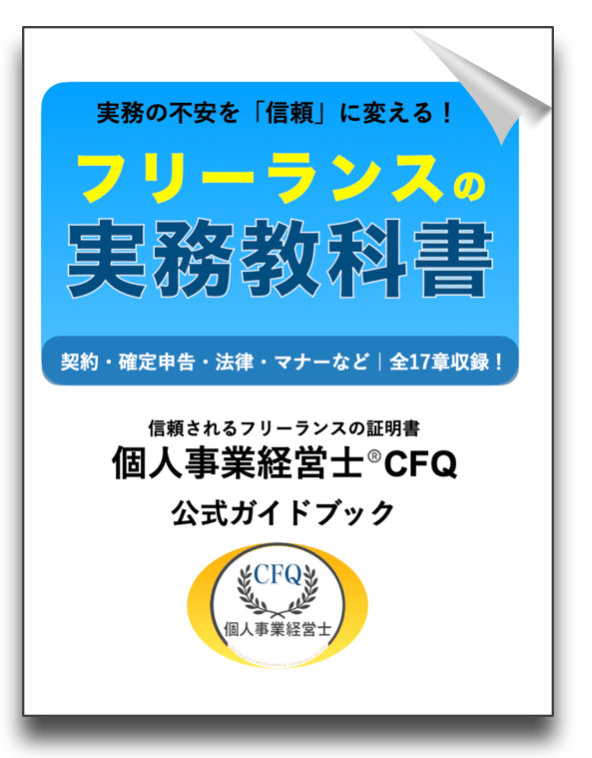
こんな人におすすめ
- フリーランス1年目で何から始めていいか分からない
- 契約書・見積書の作り方に自信がない
- 確定申告でいつも不安になる
- クライアントに対等に扱われたい
- 体系的に実務を学びたい
私自身、この参考書に出会ってから、「一人で不安」が「自信を持って対応できる」に変わりました。
あなたの「事業者としての土台」を、この1冊がしっかり支えてくれます。
【まとめ】事業とプライベートの線引きをしっかり!
確定申告で経費が否認されると、追徴課税だけでなく、延滞税や加算税も発生します。金銭的な負担もさることながら、税務署からの指摘を受けるという精神的なストレスは、本当に辛いものです。
私自身、あの封筒を開けた日のことは、今でも鮮明に覚えています。「ちゃんと調べておけばよかった」「曖昧なまま計上するんじゃなかった」と、何度も後悔しました。
でも、その経験があったからこそ、今は経費の計上に対して慎重になれたし、きちんと記録を残す習慣も身に付きました。失敗は誰にでもあります。大切なのは、その失敗から学び、次に活かすことです。
経費の計上は、フリーランスにとって大切な権利です。でも、その権利を正しく行使するためには、正しい知識が必要です。「これくらいなら大丈夫だろう」という曖昧な判断が、後々大きなトラブルを招くこともあります。
迷ったときは、自分だけで判断せず、税理士さんや信頼できる情報源に頼ってください。そして、日々の記録をきちんと残すこと。それだけで、確定申告のストレスはぐっと減ります。
フリーランスとして自由に働くためには、税務のルールを守ることが前提です。ルールを知らないまま進むのではなく、正しい知識を身につけて、自信を持って申告できるようになりましょう。そうすれば、仕事に集中できる時間も増えるし、心の余裕も生まれます。
あなたがこれから迎える確定申告が、少しでもスムーズで安心できるものになりますように。
私自身、いろいろな失敗した経験があったからこそ、今は慎重に、でも自信を持って実務を進められるようになりました。
「税務が不安…」「契約が苦手…」
そんな悩みも、正しい知識を持つことで大きな武器に変わります。
不安をそのままにするのではなく、学んで備えれば、あなたの自信につながり、その自信が信頼を生むという未来が待っています。
フリーランスの新しい資格「CFQ」は、そんなあなたの実務力を一緒に育てていきます。

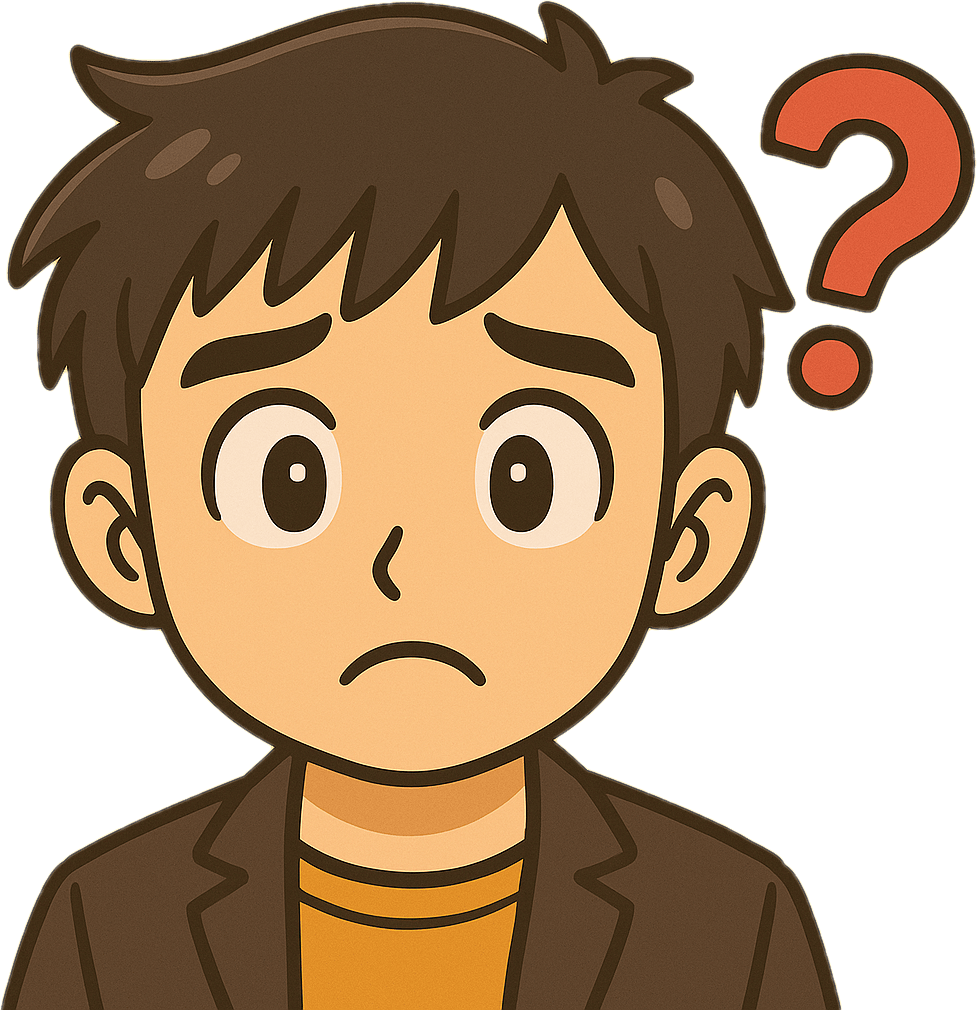 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A) CFQ(個人事業経営士)公式参考書で「実務力」を固める
CFQ(個人事業経営士)公式参考書で「実務力」を固める