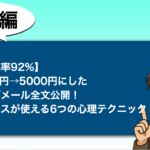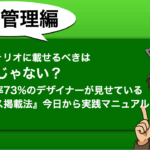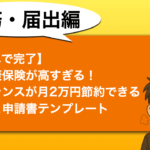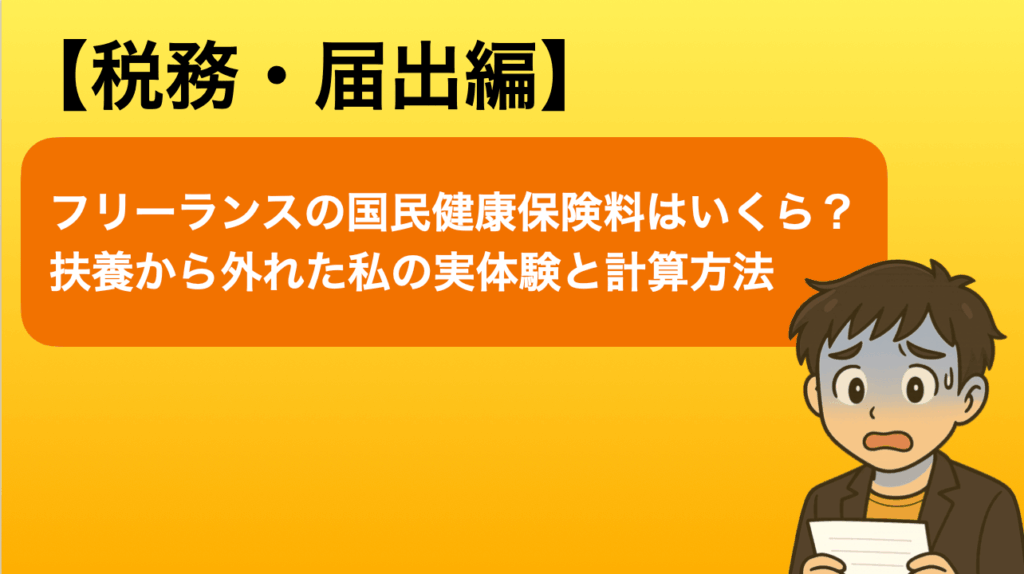
こんにちは。フリーランスひかるです。
「会社員の夫の扶養から外れたら、国民健康保険料がとんでもない金額になった…」
先月、友人からこんな相談を受けました。
実は私も同じ経験をしていて、最初に保険料の通知が届いたときは本当にびっくりしたんです。
月5万円って、まさか冗談でしょ?って感じでした。
でも今振り返ると、あの時にしっかり制度を理解して対策を立てたことで、クライアントからの信頼も得られるようになったし、税務面でも自信を持って対応できるようになりました。
フリーランスとして成長するための大切な一歩だったなと思います。
✅ この記事はこんな方におすすめ
- フリーランスになって国民健康保険料がいくらかかるか知りたい方
- 扶養から外れることになって不安を感じている方
- 保険料の計算方法や節約方法を知りたい方
- 税務や契約面でクライアントに信頼される実務力を身につけたい方
フリーランスの国民健康保険料、実際いくらかかるの?
私がフリーランスになったのは3年前。
当時は妻が扶養に入っていたのですが、妻の収入が年間130万円を超えそうになって、国民健康保険に切り替えることになりました。
正直、最初は「保険料なんて月1万円くらいでしょ?」と軽く考えていたんです。
ところが蓋を開けてみると、月額約4万5千円。年間で54万円という現実が待っていました。
国民健康保険料は主に以下の要素で決まります。
所得割 前年の所得に応じて計算される部分
均等割 加入者一人当たりの定額部分
平等割 世帯当たりの定額部分(自治体によって異なる)
資産割 固定資産税額に応じた部分(廃止している自治体も多い)
私の妻の場合、前年の所得が約350万円だったので、東京都内での計算では月額4万円を超える金額になったんです。
扶養時代は保険料ゼロだったので、家計への影響は想像以上でした。
でも、この経験があったからこそ、税務に関する知識が深まって、クライアントとの契約交渉でも「しっかりした人だな」と信頼してもらえるようになったんです。
扶養から外れるタイミングと判断基準
「いつ扶養から外れるべきか」これって本当に悩みますよね。
私も当時、妻と何度も話し合いました。
扶養の年収基準は年間130万円(月平均10万8千円)です。
ただし、この判定は「向こう1年間の収入見込み」で行われるのがポイント。
つまり、ある月に10万8千円を超えたら、その時点で扶養から外れる手続きが必要になります。
私の妻の場合、8月に単価アップの案件を複数獲得できて、月収が15万円になったタイミングで扶養を外れました。当時は「もう少し様子を見ても…」と迷ったのですが、社労士の友人から「扶養の判定は厳格だから、基準を超えたらすぐに手続きした方がいいよ」とアドバイスをもらって決断しました。
実際、扶養から外れる手続きを後回しにしてしまうと、後から差額を請求される可能性もあります。
2022年にも、扶養認定の見直しが厳格化されて、多くのフリーランスが遡って保険料を請求されるケースが報道されていました。
早めの判断と手続きが、後々のトラブルを避けるコツです。
そして何より、こうした制度をきちんと理解していることが、クライアントからの信頼獲得にもつながるんです。
国民健康保険料を安くする方法
高額な保険料にショックを受けた私は、必死に節約方法を調べました。
その結果、いくつかの有効な方法を見つけることができたんです。
1. 所得控除を最大限活用する
青色申告特別控除(最大65万円)を利用することで、所得を大幅に減らすことができます。
青色申告に変更した年は、保険料が年間約15万円安くなりました。
また、小規模企業共済やiDeCoなどの控除も積極的に活用しています。
2. 自治体の減免制度を利用する
多くの自治体では、前年比で所得が大幅に減少した場合の減免制度があります。
コロナ禍では特例的な減免もありました。
私の住む区でも、所得が前年の3割以上減少した場合は最大7割減免される制度があります。
3. 任意継続被保険者制度の検討
会社を退職してフリーランスになる場合、前職の健康保険を最大2年間継続できる制度があります。
私の知人は、この制度を利用することで月額保険料を2万円ほど節約できました。
具体例として、freee(フリー)などの会計ソフトを活用することで、青色申告の準備も格段に楽になります。
私も利用していますが、保険料の計算や節税対策のシミュレーションまでできて重宝しています。
参考URL: https://www.freee.co.jp/
これらの知識を身につけることで、クライアントとの契約条件交渉でも「税務面もしっかり考慮してくれる人だな」と評価してもらえるようになりました。
計算方法と具体的なシミュレーション
実際の計算方法を、私の体験を元にご紹介しますね。
東京都内在住、年間所得350万円の場合(令和5年度)
医療分
- 所得割: 350万円 × 7.16% = 約25万円
- 均等割: 4万5千円
後期高齢者支援分
- 所得割: 350万円 × 2.29% = 約8万円
- 均等割: 1万3千円
介護分(40歳以上)
- 所得割: 350万円 × 2.07% = 約7万2千円
- 均等割: 1万6千円
年間保険料合計: 約47万6千円(月額約4万円)
この計算を見た時、正直「高すぎる…」と思いました。でも、青色申告特別控除65万円を適用すると、課税所得が285万円になって、年間保険料は約37万円まで下がります。月額で約8千円の節約です。
私が実際に使っているのは、各自治体のホームページにある保険料計算シミュレーターです。
東京都の場合、正確な金額を事前に把握できるので、資金計画が立てやすくなりました。
この知識があることで、クライアントとの単価交渉でも「手取りベースでの収益性」を正確に伝えられるようになり、より良い条件での契約につながっています。
 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A)
Q1. フリーランスになったら、すぐに国民健康保険に加入する必要がありますか?
A:👉はい、会社の健康保険から外れた日から14日以内に手続きが必要です。遅れると保険料の遡及請求もあるので、早めの手続きをおすすめします。
Q2. フリーランスの収入が不安定でも、保険料は毎月同じ金額ですか?
A:👉保険料は前年の所得を基に年額が決定され、通常は年10回(6月〜翌年3月)の分割払いです。収入が激減した場合は減免申請ができる自治体もあります。
Q3. フリーランス1年目で前年の所得がゼロの場合、保険料はどうなりますか?
A:👉前年所得がゼロの場合、所得割はゼロになりますが、均等割や平等割は課税されます。私の自治体では年間約5万円程度でした。
Q4. フリーランスが扶養に戻ることは可能ですか?
A:👉向こう1年間の収入見込みが130万円未満になれば、再度扶養に入ることは可能です。ただし、一時的な収入減での頻繁な切り替えは避けた方が良いでしょう。
Q5. フリーランスでも健康保険料を経費にできますか?
A:👉いいえ、国民健康保険料は経費にはできませんが、社会保険料控除として所得控除の対象になります。確定申告で必ず計上しましょう。
 「フリーランスの実務」は不安がいっぱい
「フリーランスの実務」は不安がいっぱい
フリーランスの実務って、たくさんあって覚えきれない…。
フリーランスとして一人で仕事をする中で、「これ、誰にも相談できない…」と不安になる場面、ありませんか?
そんな声をもとに作られたのが、CFQ(個人事業経営士)公式参考書です。
「経営実務のスキルを持ち、信頼されるフリーランス」になるために
この参考書は、単なる制度解説ではありません。
- 届出・税務・契約・保険などの基礎知識
- リアルなケーススタディ
- その場で確認できる4択式理解テスト
といった3ステップ構成で、あなたの「なんとなく不安」を「自信」に変える実践的な教材です。
この1冊があれば、もう一人で不安にならなくていい。
あなたの「事業者としての土台」を、しっかりと支えてくれる教科書です。
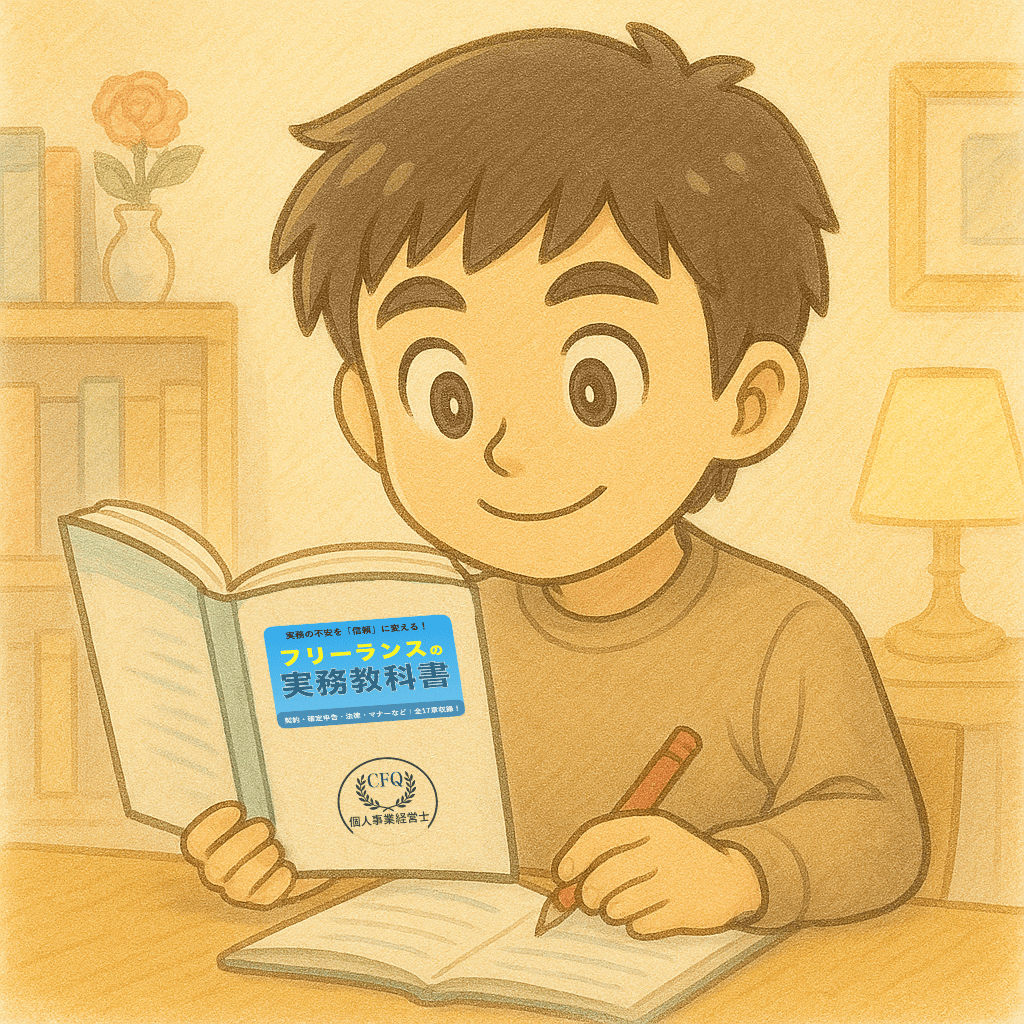
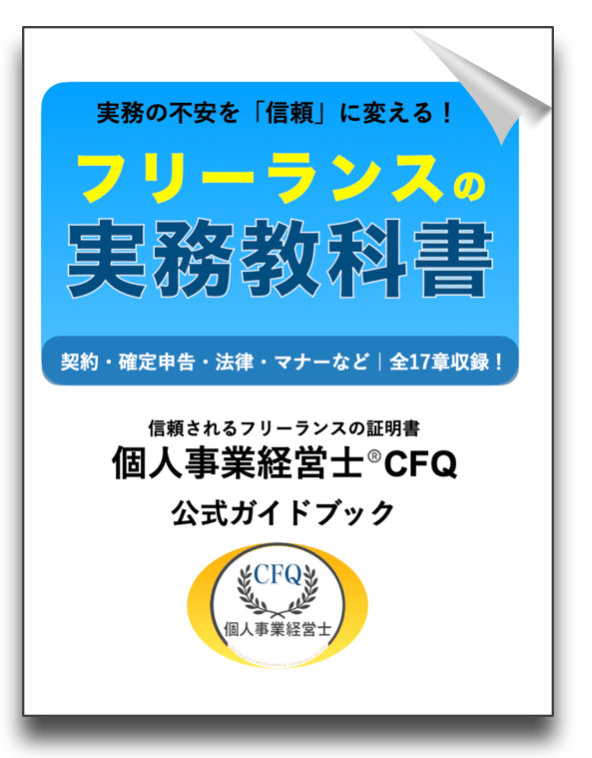
【まとめ】健康保険は…正直高い!
フリーランスの国民健康保険料は決して安くありませんが、正しい知識と対策があれば、必要以上に恐れることはありません。
私自身、最初はその金額にショックを受けましたが、今では「これも事業の必要経費の一つ」として受け入れています。
大切なのは、制度を理解して適切に対応すること。
そうすることで、クライアントからの信頼も得られるし、自分自身の事業運営にも自信が持てるようになります。
保険料の負担は重いかもしれませんが、それ以上に得られるものがあります。
まるで重いリュックを背負って山を登るようなもの。
最初はきついけれど、頂上に着いた時の景色は、軽装では決して見ることのできない素晴らしいものなんです。
あなたも今は不安に感じているかもしれませんが、一歩ずつ知識を積み重ねていけば、きっと自信を持ってフリーランスライフを送れるようになりますよ。
私自身、いろいろな失敗した経験があったからこそ、今は慎重に、でも自信を持って実務を進められるようになりました。
「税務が不安…」「契約が苦手…」
そんな悩みも、正しい知識を持つことで大きな武器に変わります。
不安をそのままにするのではなく、学んで備えれば、あなたの自信につながり、その自信が信頼を生むという未来が待っています。
CFQは、そんなあなたの実務力を一緒に育てていきます。

 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A)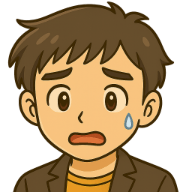 「フリーランスの実務」は不安がいっぱい
「フリーランスの実務」は不安がいっぱい