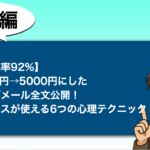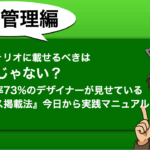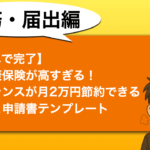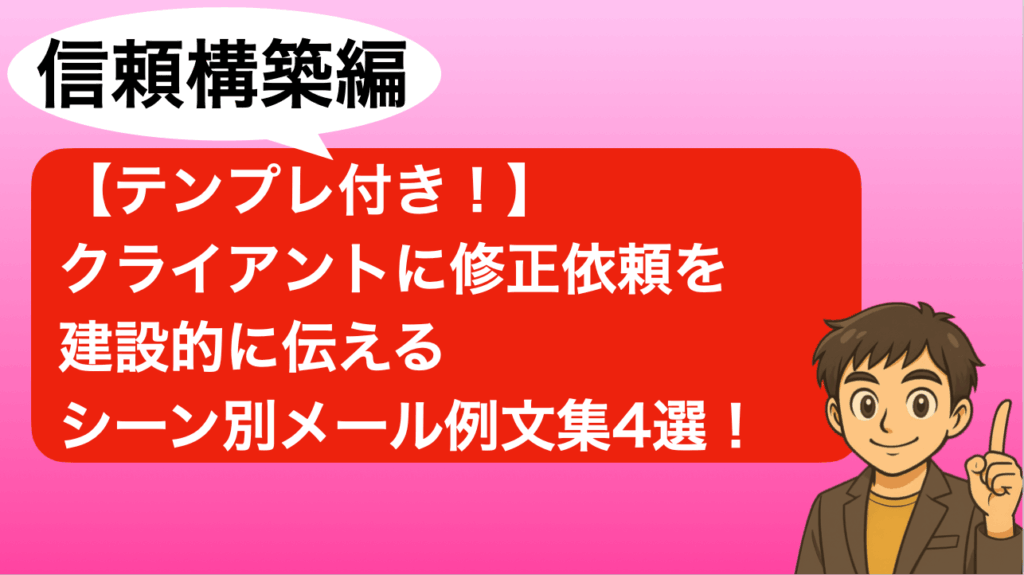
こんにちは。フリーランスひかるです。
「あれ、これってちょっと違うかも…」そう思いながらも、なかなか言い出せずに納品してしまった経験、ありませんか?
私も以前、クライアントから受け取った資料に明らかな間違いがあったのに、「指摘したら嫌われるかな」「めんどくさいやつだと思われないかな」って不安で、結局そのまま進めてしまったことがあります。
結果、納品後に大きな手戻りが発生して、双方に無駄な時間が生まれてしまいました。あの時の自分に「ちゃんと伝えなよ」って言ってあげたい。本当に悔しかったです。
クライアントへの修正依頼って、フリーランスにとって最も気を遣う場面のひとつですよね。でも実は、建設的に伝えることができれば、信頼関係はむしろ深まるんです。
この記事では、修正依頼を角が立たずに伝える方法と、すぐに使えるメールテンプレートをご紹介します。
✅ この記事はこんな方におすすめ
- クライアントに修正依頼を出すタイミングがわからない方
- 言いにくいことを伝えるのが苦手な方
- 修正依頼で関係が悪化した経験がある方
- メールの文面でいつも悩んでしまう方
- 建設的批判のスキルを身につけたい方
私が修正依頼を言えなかった、あの日の後悔
フリーランス3年目の夏のことです。あるWebサイトのライティング案件で、クライアントから参考資料として受け取ったドキュメントに、明らかな誤情報が含まれていました。
「これ、このまま記事にしたら炎上するかも…」
頭の中で警告音が鳴っていたのに、私は何も言えませんでした。「まだ経験が浅いのに生意気だと思われたら、次の依頼がなくなるかもしれない」。そんな恐怖が、正しいことを伝える勇気を奪っていました。
結果、記事は公開直後から読者の指摘を受け、クライアントは修正対応に追われることに。「ひかるさん、なんで事前に言ってくれなかったんですか」と言われた時の、あの胸の痛みは今でも忘れられません。
私は「いい人」でいようとして、結果的にクライアントにも迷惑をかけてしまったのです。信頼を守ろうとして、信頼を失った瞬間でした。
修正依頼を言えないと起こる「負のスパイラル」
修正依頼を我慢すると、実は取り返しのつかない事態を招くことがあります。
信頼関係の崩壊
「言ってくれればよかったのに」。クライアントからこの言葉を受けるのは、本当につらいものです。プロとして対等な立場で仕事をしているはずなのに、遠慮して黙っていたことで、逆に「プロ意識が足りない」と評価されてしまいます。
公正取引委員会と厚生労働省が実施した調査では、フリーランスの約4割が取引先とのトラブルを経験していることがわかっています。その多くが、「言いにくいことを言えなかった」ことから始まっているのです。
収益面での損失
修正依頼を出さずに進めた結果、大幅な手戻りが発生するケースもあります。「修正対応回数は2~3回まで」と合意していても、根本的な方向性が間違っていれば何度でもやり直しになり、報酬に見合わない工数がかかってしまいます。
さらに深刻なのは、公正取引委員会の調査で、クライアント側は修正依頼を「不当なやり直し」と認識している割合がわずか0.4%なのに対し、フリーランス側は13.7%が不当だと感じているという現実です。
認識のズレが積み重なると、無償での作業が増え続け、時給換算したら最低賃金を下回っていた、なんてことも起こります。
精神的な疲弊
「また言えなかった」という自己嫌悪。「これでいいのかな」という不安。クライアントとのやり取りのたびに胃が痛くなる。こうした状態が続くと、フリーランスという働き方そのものが苦痛になってしまいます。
実際に、修正回数が多すぎて納期の厳しい別案件が進められなくなったり、スケジュールがめちゃくちゃになったりするケースは多数報告されています。
私も一時期、クライアントからの連絡を見るだけで動悸がしていた時期がありました。「またダメ出しかな」「もう無理かも」。そんな気持ちで仕事をしても、良いものは生まれません。
修正依頼を「スマートに」伝える3つのステップ
では、どうすれば修正依頼を建設的に伝えられるのでしょうか。ここからは具体的な方法をお伝えします。
ステップ1:タイミングを見極める
修正依頼は「気づいた瞬間」が勝負です。時間が経てば経つほど、伝えにくくなります。
おすすめのタイミングは次の通りです。
初期段階での気づき 要件定義やヒアリングの段階で違和感を覚えたら、その場で確認しましょう。「念のため確認させてください」という言葉を使えば、角が立ちません。
成果物提出前 納品前なら、「確認中に気になる点が見つかりました」と伝えやすいタイミングです。完成してから伝えるよりも、制作途中での指摘の方が受け入れられやすいです。
定例ミーティング 定期的に打ち合わせがある案件なら、そのタイミングで伝えるのもスムーズです。「今週の進捗報告なのですが、ひとつ相談があります」という切り出し方が自然です。
ステップ2:建設的批判の基本「肯定→課題→提案」
建設的批判では、まず肯定的なフィードバックで相手の良い点を認め、次に改善が必要な点を具体的に指摘し、最後に解決策を提示するという「サンドイッチ形式」が効果的です。
良い例
いただいた資料、とても詳しくまとめていただきありがとうございます。
おかげで方向性がよく理解できました。
一点だけ確認させていただきたいのですが、
3ページ目のデータが2023年のものになっていますが、
最新の2024年版をご用意いただくことは可能でしょうか。
より説得力のある内容になると思いますので、ご検討いただけますと幸いです。
悪い例
資料の3ページ目、データが古いですね。
最新版に差し替えてください。違いがわかりますか?良い例では、まず感謝を伝え、相手の努力を認めた上で、「確認させていただきたい」という柔らかい表現で課題を伝えています。そして最後に「より良くなる」という前向きな理由を添えています。
ステップ3:具体的な提案をセットにする
建設的批判とは、問題の指摘だけでなく、改善策や解決策の提示がセットになっているものです。ただ「これ違います」と言うのではなく、「こうしたらいかがでしょうか」まで伝えることで、相手も対応しやすくなります。
具体例
- 「納期が厳しいです」ではなく「◯日までに中間確認をいただければ、△日の納品が可能です」
- 「仕様が曖昧です」ではなく「A案とB案、どちらのイメージでしょうか。サンプルをご用意しました」
- 「予算が足りません」ではなく「この内容ですと追加◯万円かかりますが、◯◯の範囲に絞れば現予算内で対応可能です」
すぐ使える!シーン別メールテンプレート
ここからは、実際の場面ですぐに使えるメールテンプレートをご紹介します。コピーして自分なりにアレンジしてみてください。
テンプレート1:情報の不足や誤りを指摘する場合
件名:【確認】資料について1点ご相談
◯◯様
いつもお世話になっております。ひかるです。
ご提供いただいた資料、拝見いたしました。
詳細にまとめていただき、ありがとうございます。
制作を進める中で、一点確認させていただきたい箇所がございます。
【確認事項】
・資料P.5の◯◯のデータが△△年のものとなっておりますが、
最新の□□年版をご用意いただくことは可能でしょうか。
より正確な内容で制作を進められればと思い、ご連絡いたしました。
もし最新版のご用意が難しい場合は、
現在のデータで進めることも可能ですので、
ご都合をお聞かせいただけますと幸いです。
お手数をおかけいたしますが、
ご確認のほどよろしくお願いいたします。テンプレート2:方向性のズレを修正したい場合
件名:【方向性のご確認】制作内容について
◯◯様
お世話になっております。ひかるです。
現在制作を進めております◯◯の件ですが、
より良いものをお届けしたく、ご相談がございます。
当初のご要望として「△△なイメージ」とお聞きしておりましたが、
制作を進める中で、「□□なアプローチ」の方が
ターゲット層により響くのではないかと感じております。
【ご提案内容】
・現在の方向性:△△
・ご提案したい方向性:□□
・理由:(具体的な根拠を記載)
もちろん、当初のイメージを大切にされたいお気持ちもあるかと思いますので、
一度ご意見をお聞かせいただけますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。テンプレート3:追加作業が発生する場合
件名:【ご相談】追加作業のお見積りについて
◯◯様
いつもお世話になっております。ひかるです。
◯◯の件、ご依頼ありがとうございます。
ご要望を拝見し、より良いものをご提供したいと考えております。
一点ご相談なのですが、今回のご依頼内容を拝見したところ、
当初の契約範囲を超える作業が含まれているように感じました。
【当初の契約範囲】
・△△の制作(◯ページ分)
【今回のご依頼】
・△△の制作(◯ページ分)+ □□の追加(◯ページ分)
もちろん、追加のご依頼も喜んでお受けいたしますが、
作業工数が増える分、別途お見積りをさせていただければと思います。
【お見積り】
・追加作業分:◯◯円
・納期:△日後(中間確認を含む)
もし予算のご都合がある場合は、
作業範囲を調整することも可能ですので、
お気軽にご相談くださいませ。
ご検討のほど、よろしくお願いいたします。テンプレート4:納期の調整が必要な場合
件名:【ご相談】納期について
◯◯様
お世話になっております。ひかるです。
◯◯の制作、順調に進んでおります。
一点ご相談なのですが、
より品質の高いものをお届けするため、
納期について調整をお願いできないかと考えております。
【現在の状況】
・当初納期:◯月△日
・現在の進捗:約70%完了
・課題:□□の部分で、想定よりも時間がかかっております
【ご提案】
・新しい納期案:◯月□日
・追加でご提供できる内容:△△(より丁寧な仕上げなど)
もちろん、納期厳守が最優先の場合は、
当初の予定通り対応することも可能ですが、
その場合は◯◯の範囲を調整させていただく形となります。
お忙しいところ恐縮ですが、
ご都合をお聞かせいただけますと幸いです。修正依頼が「信頼の証」になる本当の理由
ここまで読んで、「結局、言いにくいことを言うのは怖い」と思う方もいるかもしれません。
でも、考えてみてください。あなたは「何も言わずに間違ったものを納品する人」と「リスクを伝えて一緒に解決策を考えてくれる人」、どちらと仕事をしたいですか?
答えは明らかですよね。
プロとしての価値は「提案力」にある
クライアントは、あなたに「言われた通りに作る人」を求めているのではありません。「より良いものを一緒に作ってくれるパートナー」を求めているのです。
だから、建設的な修正依頼ができる人は、むしろ信頼されます。「この人は本気でプロジェクトを成功させようとしてくれている」と感じてもらえるからです。
修正依頼で深まる信頼関係
実際、私が今でも継続してお仕事をいただいているクライアントの多くは、初期の段階で「実はこう思うんです」と率直に意見を伝えた相手です。
一度、勇気を出して伝えた後、クライアントから「実は私もそう思っていたんです。言ってくれてありがとう」と言われたことがあります。
あの時の安堵感と、「この人とならいい仕事ができる」という確信は、今でも鮮明に覚えています。
スコープを守ることで、お互いが幸せになる
フリーランスとして長く活動していくためには、仕事の範囲をきちんと守ることが大切です。追加作業をなあなあで引き受けていると、結果的に自分の首を絞めることになります。
きちんと「ここからは別途お見積りになります」と伝えられる人は、クライアントからも「信頼できるプロ」として扱われます。
明日からできる!3つの小さなステップ
最後に、明日からすぐに実践できる小さなステップをご紹介します。
ステップ1:メールのテンプレートを保存しておく
この記事のテンプレートを、あなたのメールソフトやメモアプリに保存しておきましょう。いざという時にゼロから考える必要がなくなります。
GoogleドキュメントやNotionにテンプレート集を作っておくと、必要な時にすぐコピペできて便利です。
ステップ2:「確認させてください」を口癖にする
「指摘する」のではなく「確認する」。この言葉の使い方だけで、相手の受け取り方は大きく変わります。
「これ、違いますよね?」ではなく「念のため確認させてください」。この小さな違いが、大きな安心感を生みます。
ステップ3:小さな案件から練習する
いきなり大口のクライアントに修正依頼を出すのは勇気がいります。まずは、比較的関係性が良好な小規模案件で練習してみましょう。
成功体験を積み重ねることで、「ちゃんと伝えても大丈夫だ」という自信がついてきます。
 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A)
Q1. フリーランスが修正依頼を出すベストなタイミングはいつですか?
A:👉気づいた瞬間が最適です。時間が経つほど伝えにくくなりますし、修正コストも大きくなります。特に、要件定義や初期段階での違和感は、その場で確認するのがベストです。
Q2. フリーランスとして、何度も修正依頼をするのは失礼でしょうか?
A:👉建設的な理由があれば問題ありません。ただし、「なぜその修正が必要なのか」を丁寧に説明することが大切です。感情的な指摘ではなく、論理的な提案を心がけましょう。
Q3. フリーランスが修正依頼で関係を悪化させないコツは?
A:👉「肯定→課題→提案」の順番を守ることです。まず相手の良い点を認め、改善点を伝え、最後に解決策を提示する。この流れを意識するだけで、受け取られ方が大きく変わります。
 CFQ(個人事業経営士)公式参考書で「実務力」を固める
CFQ(個人事業経営士)公式参考書で「実務力」を固める
「契約が不安…」「税務が怖い…」「トラブルが心配…」
そんな「なんとなく不安」を抱えたまま、フリーランスを続けていませんか?
CFQ(個人事業経営士)公式参考書は、まさにそんな人のために作られました。
この1冊で学べること
- 届出・税務の基礎(開業届、青色申告、インボイス制度)
- 契約・法務の実務(契約書の作り方、著作権、下請法)
- 保険・リスク管理(損害賠償、PL保険、トラブル対応)
- ケーススタディ(実例から学ぶ失敗パターン)
- 4択式テスト(理解度チェック)
単なる制度解説ではなく、「明日から使える実務知識」が詰まっています。
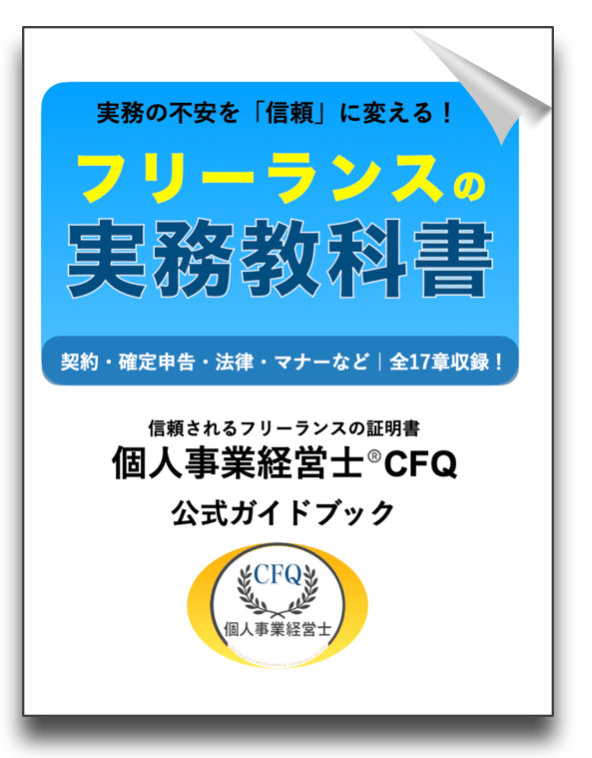
こんな人におすすめ
- フリーランス1年目で何から始めていいか分からない
- 契約書・見積書の作り方に自信がない
- 確定申告でいつも不安になる
- クライアントに対等に扱われたい
- 体系的に実務を学びたい
私自身、この参考書に出会ってから、「一人で不安」が「自信を持って対応できる」に変わりました。
あなたの「事業者としての土台」を、この1冊がしっかり支えてくれます。
【まとめ】ちゃんと言えるのがプロの証
修正依頼を建設的に伝えることは、決して「わがまま」でも「生意気」でもありません。むしろ、プロとして当然の姿勢です。
最初は勇気がいるかもしれません。でも、一度伝えてみると、意外と大丈夫だったりします。そして何より、「ちゃんと言えた」という小さな成功体験が、あなたの自信になります。
クライアントとの関係は、遠慮し合う関係ではなく、お互いに率直に意見を言い合える関係が理想です。そのためには、まず自分から一歩踏み出すことが大切です。
今日ご紹介したテンプレートやステップを使って、ぜひ明日から実践してみてください。きっと、仕事がもっと楽しくなるはずです。
あなたには、正しいことを伝える力があります。その力を、自信を持って使ってくださいね。
私自身、いろいろな失敗した経験があったからこそ、今は慎重に、でも自信を持って実務を進められるようになりました。
「税務が不安…」「契約が苦手…」
そんな悩みも、正しい知識を持つことで大きな武器に変わります。
不安をそのままにするのではなく、学んで備えれば、あなたの自信につながり、その自信が信頼を生むという未来が待っています。
フリーランスの新しい資格「CFQ」は、そんなあなたの実務力を一緒に育てていきます。

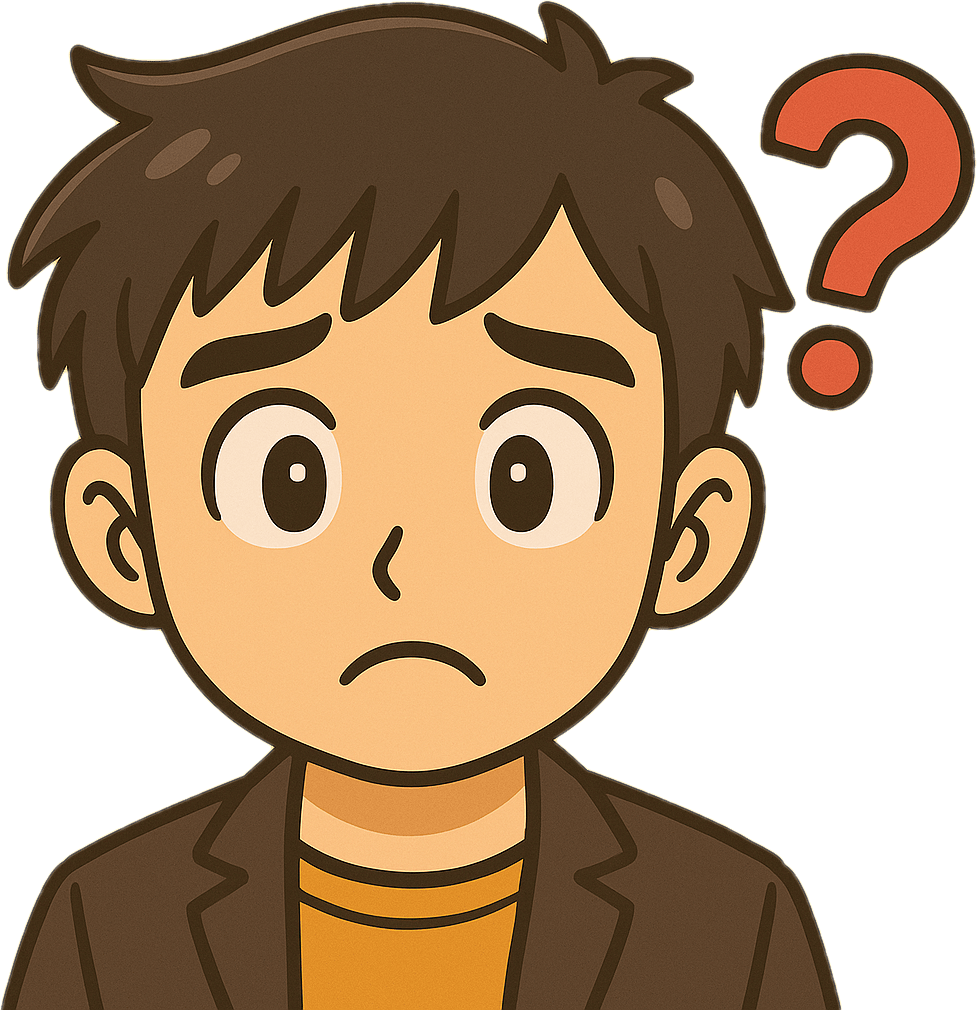 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A) CFQ(個人事業経営士)公式参考書で「実務力」を固める
CFQ(個人事業経営士)公式参考書で「実務力」を固める