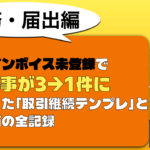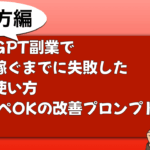こんにちは。フリーランスひかるです。
インボイス制度が始まって2年が経ち、私の周りのフリーランス仲間からこんな声をよく聞くようになりました。「2割特例って、いつまで使えるんだっけ?」「終わったら、急に税金が増えるって本当?」そんな不安を抱えながらも、目の前の仕事に追われて後回しにしてしまう気持ち、すごくわかります。
実は私も去年、この「2割特例の期限」を意識せずに過ごしていて、ある日ふと計算したときに愕然としたんです。このまま何も対策しないまま特例が終わったら、手取りが一気に減ってしまう。そのことに気づいた瞬間、背筋がゾッとしました。
今日は、そんな私の失敗から学んだ「2割特例が終わる前に絶対やっておくべき計算方法」と、終了後の対策について、できるだけわかりやすくお話ししていきます。
✅ この記事はこんな方におすすめ
- インボイス登録したけど、2割特例がいつまで使えるか曖昧な方
- 特例終了後の税負担がどれくらい増えるか不安な方
- 手取りを維持するために今からできる対策を知りたい方
- クライアントとの単価交渉に自信が持てない方
- 確定申告や消費税の計算が苦手で先延ばしにしている方
2割特例は「いつまで」使えるのか|期限を知らないと後悔する理由
インボイス制度の2割特例は、2023年10月1日から2026年9月30日までの期間に対応した3年間の経過措置です。具体的には、この期間を含む課税期間で利用できるため、個人事業主の場合は2026年分(2026年1月1日〜12月31日)の確定申告まで使える計算になります。
私がこの期限を本気で意識し始めたのは、実は最近のことでした。フリーランス仲間のデザイナーさんが、「2027年からいきなり税金が増えるって聞いて焦ってる」と言っていたんです。彼女は年間売上が約800万円。2割特例を使っている今は、消費税の納税額が年間約16万円で済んでいます。
でも、原則課税に戻ったら、経費率によっては納税額が40万円を超える可能性もある。差額の24万円って、フリーランスにとっては1〜2ヶ月分の生活費に相当します。それが突然消えるって、考えるだけで怖くないですか。
特に注意が必要なのは、「なんとなく延長されるだろう」と楽観視してしまうこと。税制は基本的に期限通りに終わります。今から準備しないと、2027年の確定申告で「こんなはずじゃなかった」と後悔することになるんです。
国税庁の公式サイトでも、この3年間という期限は明確に示されています。期限を正確に把握して、残り時間で何ができるかを考えることが、今一番大切なステップなんです。
参考URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_keizai.htm
2割特例の「計算方法」を理解すれば、終了後の衝撃が見えてくる
2割特例の計算は、実はとてもシンプルです。「預かった消費税×20%」を納税すればいい。たとえば年間売上が600万円(税込660万円)の場合、消費税60万円の2割、つまり12万円を納めることになります。
私が初めてこの計算をしたとき、「これって結構お得なのでは?」と感じました。でも、問題はその次です。2割特例が終わったら、原則課税または簡易課税のどちらかを選ぶことになります。
原則課税の場合は「預かった消費税−支払った消費税」を納税します。経費が少ない業種(ライターやコンサルタントなど)の場合、支払った消費税が少ないため、納税額が大幅に増えるんです。
実際に計算してみましょう。年間売上660万円(消費税60万円)、経費が年間110万円(消費税10万円)の場合、原則課税での納税額は「60万円−10万円=50万円」。2割特例の12万円と比べると、なんと38万円も増えることになります。
一方、簡易課税を選ぶと「預かった消費税×みなし仕入率」で計算できます。たとえばサービス業(第五種事業)なら、みなし仕入率は50%。同じ売上なら「60万円×(1−0.5)=30万円」の納税。それでも2割特例より18万円増えますが、原則課税よりは負担が軽くなります。
このシミュレーションを見たとき、私は正直焦りました。「今の手取りがこんなに減るの?」って。でも、逆に言えば、今のうちにこの数字を知っておけば、対策を立てられるということでもあります。
会計ソフトを使えば、こうしたシミュレーションは簡単にできます。たとえば「freee」や「マネーフォワード クラウド確定申告」では、インボイス制度に対応した消費税計算機能が充実しています。無料プランでも基本的な計算はできるので、まずは試してみるといいかもしれません。
参考URL: https://www.freee.co.jp/
「終わったら」どうなる? 私が実践した3つの対策
2割特例が終わる前に、私が実際に取り組んだ対策を3つ紹介します。どれも難しいことではなく、今日から始められることばかりです。
1. 経費の見直しと記録の徹底
まず取り組んだのが、経費の「取りこぼし」をなくすことでした。原則課税になれば、支払った消費税が控除できます。つまり、経費が多ければ多いほど納税額を抑えられるんです。
私の場合、これまで「まあいいか」と記録していなかった細かい経費がたくさんありました。打ち合わせのカフェ代、資料購入費、セミナー参加費。これらをきちんと記録し始めたら、年間で20万円以上の経費が増えました。その分、消費税の控除額も約2万円増える計算です。
レシートをスマホで撮影するだけで記録できる会計アプリを使えば、面倒な作業もかなり楽になります。私は移動中にサッと撮って、後で分類するだけ。この習慣だけで、確定申告が驚くほど楽になりました。
2. 簡易課税の届出を検討する
次に検討したのが、簡易課税制度の活用です。簡易課税を選択するには、前年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
私の業種(ライター・コンサル)の場合、経費が少ないため、簡易課税の方が有利になる可能性が高い。実際に計算してみたら、原則課税より年間15万円ほど納税額が減ることがわかりました。
ただし、簡易課税は一度選ぶと2年間は変更できません。売上や経費の状況が大きく変わる可能性がある場合は、慎重に判断する必要があります。税理士さんに相談したところ、「数年分のシミュレーションをしてから決めるといい」とアドバイスをもらいました。
3. 単価交渉の準備と実践
そして最後に、一番勇気が要ったのが単価交渉です。「消費税の負担が増えるから値上げしたい」とは言いにくいですよね。でも、実はこれ、正当な理由なんです。
私が実践したのは、「価値の再提示」を軸にした交渉でした。「消費税負担が増えるので」ではなく、「これまでの実績と、今後提供できる価値を考えると、この金額が適正だと思っています」という伝え方です。
具体的には、過去の成果物をまとめた資料を作り、クライアントにもたらした価値を数字で示しました。結果、主要クライアント2社から15〜20%の単価アップを了承してもらえたんです。このとき感じたのは、「ちゃんと準備して伝えれば、わかってくれる人はいる」ということでした。
もちろん、全てのクライアントがすぐに応じてくれるわけではありません。でも、何もせずに手取りが減るより、チャレンジする方がずっといい。そう思えるようになったのは、数字で自分の状況を理解できたからこそです。
今すぐ始める「あの方法」|手取りを守るためのロードマップ
ここまで読んでくださった方の中には、「で、結局何から始めればいいの?」と思っている方もいるかもしれません。そこで、今すぐできる具体的なステップをまとめました。
ステップ1:現状を数字で把握する(今週中)
まずは会計ソフトやExcelを使って、自分の売上・経費・消費税額を整理します。過去1年分のデータがあれば十分です。「預かった消費税」と「支払った消費税」を計算し、2割特例と原則課税、簡易課税それぞれでシミュレーションしてみましょう。
ステップ2:有利な方式を選ぶ(今月中)
シミュレーション結果をもとに、原則課税と簡易課税のどちらが有利か判断します。判断が難しい場合は、税理士や商工会議所の相談窓口を活用するのがおすすめです。無料相談を実施している自治体も多いので、ぜひ活用してみてください。
たとえば、東京商工会議所では無料の税務相談を定期的に開催しています。事前予約制ですが、30分程度でプロのアドバイスが受けられます。
参考URL: https://www.tokyo-cci.or.jp/
ステップ3:届出書の準備(2〜3ヶ月以内)
簡易課税を選ぶ場合、2026年12月31日までに税務署へ届出が必要です。書類作成自体は難しくありませんが、ミスがあると受理されないこともあります。不安な方は、税理士に依頼するか、国税庁のサイトで記入例を確認しながら進めましょう。
ステップ4:経費管理の仕組み化(継続的に)
レシート管理アプリや会計ソフトを活用し、日々の経費記録を習慣化します。「後でまとめてやろう」は危険。月1回でいいので、記録を見直す時間を作ることが大切です。
ステップ5:単価交渉の準備(3〜6ヶ月以内)
実績資料を作成し、主要クライアントとの対話の機会を探ります。いきなり「値上げしたい」ではなく、「今後の契約について相談させてください」という柔らかい入り方がおすすめです。
この5ステップを実践すれば、2027年以降の消費税負担増にも慌てずに対応できます。私自身、この流れで準備を進めたことで、不安が大きく減りました。今は「どうにかなる」ではなく、「ちゃんと準備できている」という安心感があります。
 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A)
Q1. フリーランスがインボイス2割特例を使わない選択肢はありますか?
A:👉はい、あります。2割特例は任意の制度なので、使わずに原則課税や簡易課税を選ぶこともできます。ただし、多くの場合2割特例が最も有利なので、特別な理由がない限りは利用するのがおすすめです。たとえば、設備投資で大きな支出があった年は、原則課税の方が還付を受けられる可能性があります。
Q2. 2割特例が終わった後、フリーランスは消費税をいくら払うことになりますか?
A:👉それぞれの売上や経費によって異なりますが、一般的には2〜5倍に増えることが多いです。年間売上600万円、経費が少ない業種の場合、2割特例では約12万円だったのが、原則課税では40〜50万円になることもあります。だからこそ、事前のシミュレーションが重要なんです。
Q3. フリーランスが簡易課税を選ぶべきケースとは?
A:👉経費が少ない業種(ライター、デザイナー、コンサルタントなど)は、簡易課税が有利になることが多いです。逆に、外注費や仕入れが多い業種は原則課税の方がいい場合もあります。判断に迷ったら、両方で計算してみるか、専門家に相談するのが確実です。
Q4. 2割特例の計算方法を間違えて申告した場合、フリーランスはどうなりますか?
A:👉修正申告または更正の請求が必要になります。納税額が少なかった場合は延滞税がかかる可能性もあります。逆に多く払いすぎていた場合は、還付を受けられます。いずれにしても、正確な計算が大切なので、不安な場合は税理士に相談しましょう。
Q5. フリーランスがインボイス登録を取りやめることはできますか?
A:👉はい、可能です。「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すれば、登録を取り消せます。ただし、取り消すとクライアントが仕入税額控除できなくなるため、契約に影響が出る可能性があります。慎重に判断する必要があります。
 そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!
そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!
フリーランスの実務や疑問を解決するためには、「フリーランスの実務教科書」をお勧めします。
この参考書は、単なる理論の解説ではありません。
- 届出・税務・契約・保険などの基礎知識
- 実際に起こる事例でケーススタディ
- 4択式テストで理解度をチェック
といった3ステップ構成で、あなたの不安を「自信」に変える実践的な教材です。
もう一人で不安にならなくていい。
あなたの「フリーランスとしての信用」をしっかり支えてくれる教科書です。
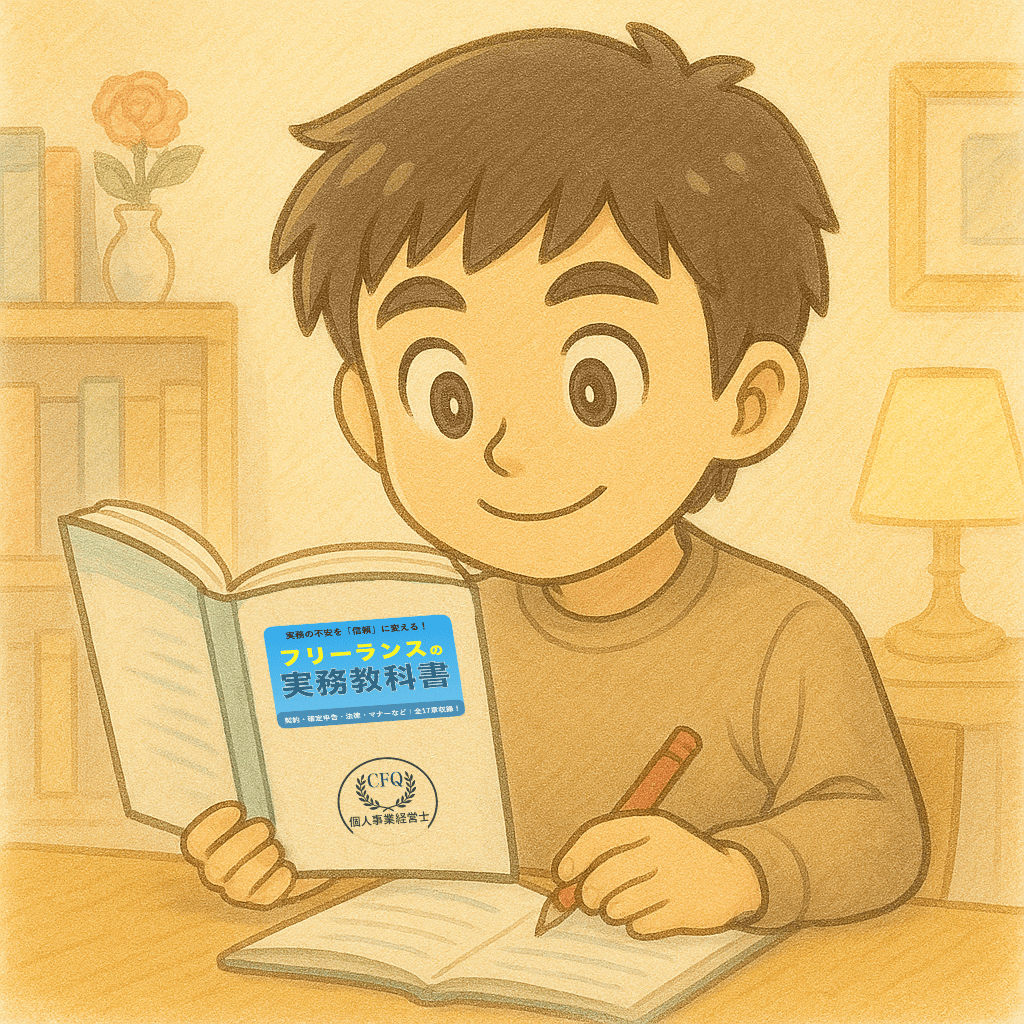
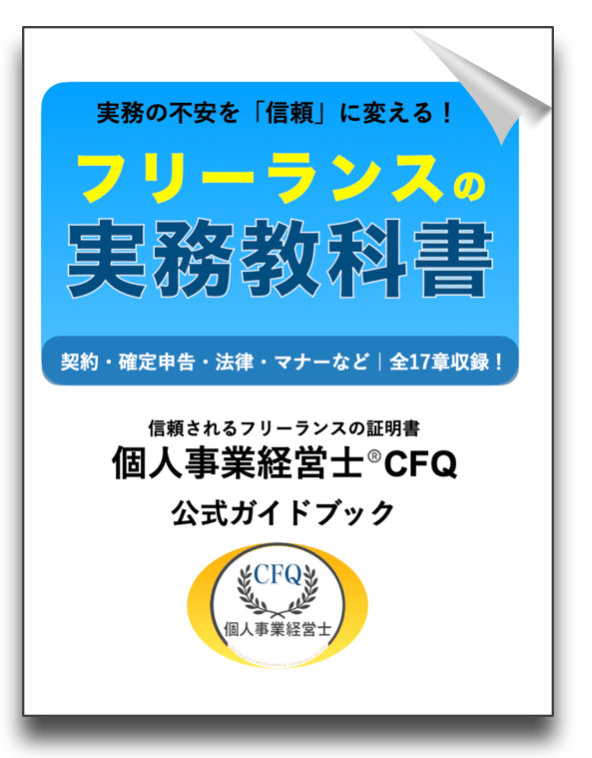
【まとめ】数字を知ることが、不安を安心に変える第一歩
インボイス2割特例が終わったら、手取りが減る。この事実を知ったとき、私は正直怖かったです。でも、きちんと計算して、対策を立てることで、その不安は「やるべきこと」に変わりました。
大切なのは、目を背けずに現実を見ること。そして、今できることから一つずつ始めること。それだけで、2027年以降も慌てずに仕事を続けられます。
税金のことって、どうしても後回しにしてしまいがちですよね。でも、後回しにすればするほど、選択肢は減っていきます。逆に、今動けば、まだ間に合います。単価交渉だって、経費の見直しだって、今年中に始めれば十分に間に合うんです。
あなたが積み上げてきた実績と信頼は、きちんと評価されるべきもの。税金が増えるからといって、手取りを諦める必要はありません。ちゃんと準備して、ちゃんと伝えれば、道は開けます。
2割特例が使える残り時間は、決して長くありません。でも、この記事を読んだあなたなら、もう大丈夫。数字を知って、行動するだけです。一歩ずつでいいので、今日から始めてみませんか。
私自身、いろいろな失敗した経験があったからこそ、今は慎重に、でも自信を持って実務を進められるようになりました。
「税務が不安…」「契約が苦手…」
そんな悩みも、正しい知識を持つことで大きな武器に変わります。
不安をそのままにするのではなく、学んで備えれば、あなたの自信につながり、その自信が信頼を生むという未来が待っています。
フリーランスの新しい資格「CFQ」は、そんなあなたの実務力を一緒に育てていきます。

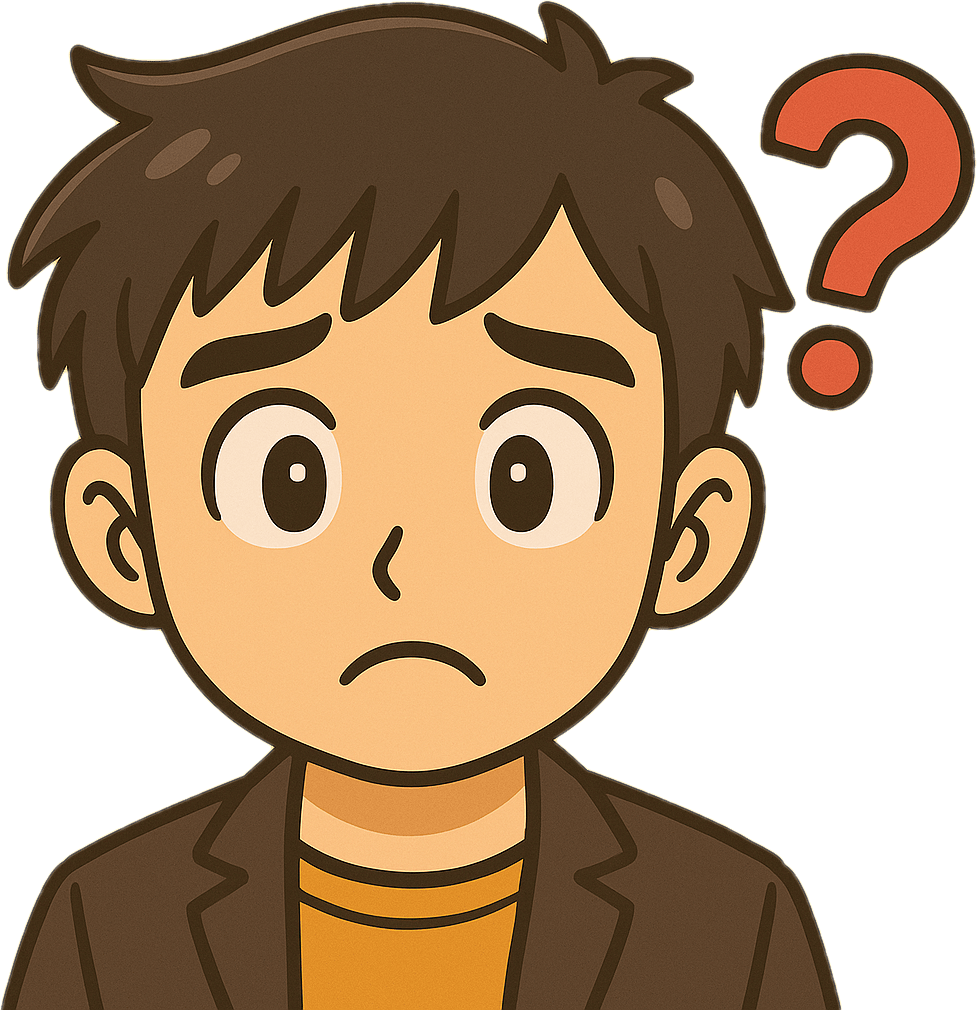 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A) そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!
そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!