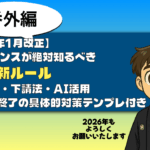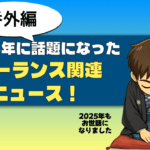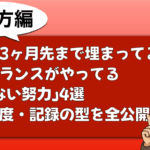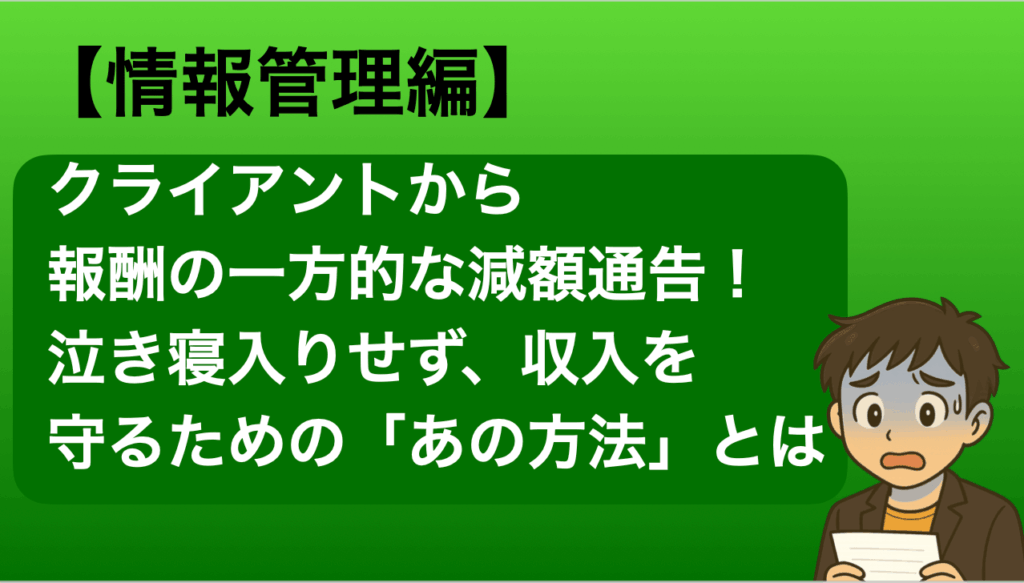
こんにちは。フリーランスひかるです。
つい半年前のことです。3年近く継続していたクライアントから突然メールが届きました。「今月から単価を30%減額させてください」。理由は「予算が厳しくなったため」の一言だけでした。
契約書には減額についての取り決めなんて一切ありません。でも、私は何も言えませんでした。「断ったら切られるかもしれない」その恐怖が頭をよぎったんです。結局、私は黙って受け入れてしまいました。
あなたも同じような経験、ありませんか?
フリーランスとして働いていると、クライアントとの力関係で「NO」と言えない場面が必ず訪れます。特に報酬の減額を一方的に通告されたとき、多くの人が泣き寝入りしてしまうのが現実です。
でも実は、2024年11月から施行された新しい法律によって、こうした一方的な減額は「禁止」されているんです。知っていましたか?
今回は、私自身の失敗談も交えながら、報酬の一方的な減額にどう対処すべきか、そして収入を守るために今すぐできる「あの方法」について、じっくりお話しします。
✅ この記事はこんな方におすすめ
- クライアントから突然の減額通告を受けて戸惑っているフリーランスの方
- 契約書がない、または曖昧な条件で仕事を受けている方
- 「言いたいことが言えない」とクライアントとの関係に悩んでいる方
- 法律や契約について不安があり、どう対処すればいいかわからない方
- フリーランスとしての収入を安定させ、正当な報酬を守りたい方
なぜフリーランスは報酬減額を受け入れてしまうのか
立場の弱さが生む「言えない空気」
フリーランスとして5年間働いてきた中で、私が一番苦しかったのは「立場の弱さ」でした。
会社員時代は対等に意見を言えた相手でも、フリーランスになった途端に関係性が変わります。クライアントは「発注する側」、私たちは「受ける側」。この構図が、無意識のうちに「言えない空気」を作り出してしまうんです。
実際に私が減額を受け入れたときも、頭の中ではこんな声がグルグル回っていました。
「ここで断ったら次の仕事がなくなる」「他のフリーランスに替えられるかもしれない」「文句を言う人は使いにくいと思われる」
これって、まるで恋人に振られるのが怖くて何も言えない状態に似ています。大切な関係だからこそ、波風を立てたくない。その気持ち、すごくわかります。
契約書がないことの怖さ
もう一つ、私が黙ってしまった理由があります。それは「契約書を交わしていなかった」ことです。
最初は軽い気持ちでした。「信頼関係があるから大丈夫」「面倒だし、相手も嫌がるかも」そんな風に考えて、メールのやり取りだけで仕事を始めてしまったんです。
でもトラブルが起きたとき、契約書がないってこんなにも無力なんだと思い知らされました。「言った・言わない」の水掛け論になり、結局自分が折れるしかなくなります。
契約書は「疑いの証」ではなく「お互いを守る盾」なんです。これに気づくのが遅すぎました。
相談する場所を知らない孤独
フリーランスは基本的に一人です。職場の同僚もいなければ、上司に相談することもできません。
減額通告を受けたとき、私は誰にも相談できませんでした。友人に話しても「大変だね」と同情されるだけで、具体的な解決策は得られません。弁護士に相談するのは敷居が高いし、お金もかかりそう。
結果として、一人で抱え込んで、一人で決断して、一人で後悔する。これがフリーランスの孤独な現実でした。
でも今なら言えます。相談できる場所は、実はたくさんあるんです。知らなかっただけなんですよね。
2024年11月施行「フリーランス新法」が変えたもの
報酬の減額が法律で禁止された
あの日、減額を受け入れてから半年後、私は「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(通称:フリーランス新法)の施行を知りました。
この法律では、発注者による一方的な報酬減額が明確に「禁止」されています。つまり、私が経験したような突然の30%減額は、法律違反だったんです。
具体的には、以下のような行為が禁止されています。
給付内容の不当な変更の禁止 成果物や作業内容が変わっていないのに、報酬を勝手に減らすことはできません。
給付受領後の減額禁止 納品後に「やっぱり予算がないから半額で」なんて言うのも違法です。
不当な経済上の利益提供要請の禁止 「次の仕事を出すから今回は安くして」といった取引も問題になる可能性があります。
もし半年前にこの法律があったら、私は毅然と断れたかもしれません。少なくとも、「これは違法です」と伝える根拠を持てたはずです。
発注時の書面交付が義務化
フリーランス新法では、もう一つ重要なルールが定められました。それが「発注時の書面交付義務」です。
これまでは口約束やメールだけで仕事を受けることも多かったと思います。でも今は、クライアント側が以下の内容を書面(電子メールも可)で明示しなければなりません。
- 業務の内容
- 報酬額
- 支払期日
- 業務の実施期間や納期
この義務化によって、「言った・言わない」のトラブルが大幅に減ることが期待されています。書面があれば、後から報酬を減額しようとしても、証拠として対抗できますからね。
実は大手IT企業では、この法律施行後にフリーランス向けの契約書フォーマットを全面的に見直したというニュースもありました。企業側も真剣に対応しているんです。
違反した場合の罰則
「でも、法律があっても守らない会社はどうせいるでしょ?」
そう思う気持ち、よくわかります。私もそう思っていました。
ただ、フリーランス新法には罰則規定があります。違反した企業には、公正取引委員会や厚生労働省から勧告や命令が出され、従わない場合は企業名が公表されます。さらに悪質な場合は、50万円以下の罰金が科されることもあります。
もちろん、罰則があるからといってすべてが解決するわけではありません。でも、少なくとも「知らなかった」では済まされない時代になったんです。
フリーランスである私たちも、この法律を知り、自分の権利を主張できる準備をしておく必要があります。
一方的な減額通告を受けたときの「あの方法」
まずは冷静に「証拠」を集める
減額通告を受けたら、まず何をすべきか。答えは「証拠を集めること」です。
感情的になって「ふざけるな!」とメールを送りたくなる気持ちはよくわかります。私もそうでしたから。でも、そこをグッとこらえて、冷静に行動することが大切です。
具体的には以下のような証拠を保存しておきましょう。
元の契約内容がわかるもの メール、チャット、見積書、発注書など、最初に合意した報酬額がわかる資料すべて。
減額通告の記録 口頭で言われた場合も、後からメールで「先ほどお話しいただいた減額の件について確認させてください」と送り、文字に残すのがポイントです。
業務内容に変更がないことの証明 納品物の内容、作業範囲、期間などが当初の契約から変わっていないことを示すもの。
私の場合、契約書がなかったことが致命的でした。でもメールのやり取りは残っていたので、それが唯一の武器になりました。
証拠は「戦うための武器」であると同時に、「自分を守る盾」でもあります。感情よりも先に、証拠を固めましょう。
相談窓口を活用する具体的ステップ
証拠を集めたら、次は相談です。一人で悩む必要はありません。
フリーランスのトラブルに対応してくれる窓口は、実はたくさんあります。私が実際に利用して良かったのが「フリーランス・トラブル110番」です。
フリーランス・トラブル110番 厚生労働省が委託して第二東京弁護士会が運営している無料相談窓口です。電話番号は0120-532-110。メールでの相談も可能で、弁護士が直接アドバイスしてくれます。
参考URL:https://freelance110.mhlw.go.jp/
実際に電話してみると、思っていた以上に親身になって話を聞いてくれました。「あなたのケースは法律違反の可能性が高いです」とはっきり言ってもらえたことで、私は初めて「自分は間違っていなかった」と思えたんです。
他にも、以下のような窓口があります。
公正取引委員会の相談窓口 フリーランス新法に関する相談を受け付けています。
下請かけこみ寺 中小企業庁が運営する相談窓口。報酬の支払いトラブルなどに対応しています。
法テラス 経済的に余裕がない場合は、無料法律相談を利用できます。
相談するときのポイントは、感情的にならず、事実を整理して伝えることです。「いつ、誰が、何を言ったか」を時系列でまとめておくと、相談がスムーズに進みます。
交渉するときの「伝え方」
相談窓口でアドバイスをもらったら、いよいよクライアントとの交渉です。
ここで大切なのは、感情的に責めるのではなく、「法律を根拠にした冷静な交渉」を心がけることです。
私が実際に使った伝え方を紹介します。
「お忙しいところ恐れ入ります。先日ご提案いただいた報酬減額の件ですが、2024年11月に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法において、業務内容に変更がない場合の一方的な報酬減額は禁止されています。今回、業務内容に変更はないと認識しておりますので、当初の契約通りの報酬でお願いしたく存じます。ご確認いただけますでしょうか」
ポイントは以下の3つです。
法律名を具体的に挙げる 相手に「これは違法なんだ」と認識してもらうため。
感情ではなく事実を述べる 「ひどい」「納得できない」ではなく、「業務内容に変更がない」という事実を伝える。
丁寧な言葉遣いを保つ 関係性を壊さないためにも、礼儀正しさは大切です。
もちろん、それでも相手が応じない場合もあります。その場合は、相談窓口で得たアドバイスをもとに、次のステップ(調停や訴訟)も視野に入れる必要があります。
でも多くの場合、法律を根拠にした冷静な交渉で解決できることが多いんです。実際、私のケースも最終的には元の報酬額に戻してもらえました。
収入を守るために今日からできること
契約書を必ず交わす習慣をつける
減額トラブルを防ぐ一番の方法は、最初から「契約書を交わすこと」です。
「契約書なんて面倒」「相手に失礼じゃないかな」そう思う気持ちはわかります。でも、契約書はお互いの認識をすり合わせ、トラブルを未然に防ぐための大切なツールなんです。
私は今、どんなに小さな案件でも必ず契約書を交わすようにしています。最初は勇気が要りましたが、今ではそれが当たり前になりました。
契約書には最低限、以下の項目を入れましょう。
- 業務内容の詳細
- 報酬額と支払条件
- 納期と修正回数
- 契約解除の条件
- 報酬変更がある場合の条件
「でも、契約書の作り方がわからない」という方も多いと思います。そんなときは、フリーランス向けの契約書テンプレートを活用するのがおすすめです。経済産業省のウェブサイトでも、無料でダウンロードできるテンプレートが公開されています。
契約書を交わすことで、クライアントとの関係が「信頼で結ばれたビジネスパートナー」になります。これは決して失礼なことではありません。むしろ、プロとしての姿勢を示すことにつながるんです。
賠償責任保険への加入を検討する
もう一つ、収入を守るために考えてほしいのが「賠償責任保険」への加入です。
フリーランスとして働いていると、納品物に不備があったり、情報漏洩のリスクがあったり、さまざまなトラブルの可能性があります。そんなとき、保険に入っていれば金銭的な負担を軽減できます。
私が加入しているのは「フリーランス協会のベネフィットプラン」です。年会費1万円で、賠償責任保険やケガの補償、さらには福利厚生サービスも受けられます。
参考URL:https://www.freelance-jp.org/
他にも、以下のような保険があります。
あんしん財団 月額2,000円程度で、ケガの補償や賠償責任保険が受けられます。
損害保険各社のフリーランス向けプラン 東京海上日動、三井住友海上などが提供しています。
保険は「万が一」のときの安心材料です。トラブルが起きてからでは遅いので、今のうちに検討してみてください。
複数のクライアントを持つリスク分散
最後に、もう一つ大切なことをお伝えします。それは「収入源を分散させること」です。
私が減額を受け入れてしまった最大の理由は、そのクライアントからの収入が全体の70%を占めていたからです。切られたら生活できない。その恐怖が、私を黙らせました。
でも今は、5〜6社のクライアントと取引をしています。一つのクライアントからの収入は、全体の30%以下に抑えるようにしているんです。
これはまるで、卵を一つのカゴに盛らないことに似ています。一つのカゴを落としても、他のカゴの卵は無事です。
もちろん、最初から複数のクライアントを持つのは難しいかもしれません。でも、少しずつ新しい取引先を開拓していくことで、徐々にリスクは分散されていきます。
収入源が分散されると、心に余裕が生まれます。「このクライアントに嫌われたらどうしよう」という恐怖から解放され、対等な関係を築けるようになるんです。
 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A)
Q1. フリーランスが減額を拒否したら、次の仕事がもらえなくなりませんか?
A:👉その心配、すごくよくわかります。私も同じことを考えていました。
でも実際のところ、法律に基づいて正当な主張をしたからといって、すぐに契約を切られることは少ないです。なぜなら、企業側も新しいフリーランスを探すのは手間がかかるし、あなたとの信頼関係を大切にしている場合が多いからです。むしろ、黙って減額を受け入れることで「この人は何を言っても大丈夫」と思われ、今後さらに不利な条件を提示される可能性もあります。正当な主張は、あなた自身を守るだけでなく、クライアントとの関係を「対等なビジネスパートナー」に変えるきっかけにもなるんです。
Q2. フリーランス新法は個人事業主全員に適用されますか?
A:👉基本的には、従業員を使用していない個人事業主や一人法人が対象です。
ただし、発注者が「法人」であることが前提になります。個人間の取引は対象外なので注意してください。
また、フリーランス新法は「継続的な業務委託」を想定していますが、単発の案件でも書面交付義務など一部の規定は適用されます。詳しくは、公正取引委員会のQ&Aページで確認できます。
参考URL:https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited/fllaw_qa.html
Q3. 口頭での減額通告は証拠にならないのでしょうか?
A:👉口頭での通告も、もちろん減額の事実としては有効です。
ただ、後から「そんなことは言っていない」と否定される可能性があるため、必ず文字に残すことをおすすめします。具体的には、口頭で減額を言われたら、すぐにメールで「先ほどお話しいただいた報酬減額の件について、詳細を確認させてください」と送りましょう。相手が返信すれば、それが証拠になります。
もし可能なら、打ち合わせの際に録音しておくのも一つの方法です(ただし、相手に無断での録音は信頼関係を損なう可能性があるので慎重に)。
Q4. フリーランス向けの相談窓口は本当に無料ですか?弁護士費用はかかりませんか?
A:👉フリーランス・トラブル110番をはじめ、多くの公的な相談窓口は無料で利用できます。
相談するだけなら費用は一切かかりません。弁護士が対応してくれる窓口でも、最初の相談は無料です。
ただし、実際に訴訟や調停を起こす場合は、弁護士費用が発生します。その場合でも、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、費用を立て替えてもらえたり、分割払いにできたりします。
まずは無料相談を気軽に利用してみてください。一人で悩むより、専門家の意見を聞くだけで心が軽くなることもあります。
Q5. フリーランスが減額を受け入れざるを得ないケースもありますか?
A:👉残念ながら、現実には「受け入れざるを得ない」と感じるケースもあります。
たとえば、クライアントが本当に経営難で倒産寸前の場合、減額を拒否しても報酬そのものが支払われなくなるリスクがあります。また、業界全体の相場が下がっている場合、他のフリーランスも同じ条件で受けているため、自分だけ拒否するのが難しいこともあります。
でも、そんなときでも「無条件で受け入れる」のではなく、交渉の余地を探ることが大切です。「減額の代わりに契約期間を延長する」「他の業務も追加で受注する」など、自分にとってメリットのある条件を提示してみましょう。
法律は武器ですが、同時に柔軟な交渉も必要です。あなた自身が納得できる形を探すことが、一番大切なんです。
 そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!
そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!
フリーランスの実務や疑問を解決するためには、「フリーランスの実務教科書」をお勧めします。
この参考書は、単なる理論の解説ではありません。
- 届出・税務・契約・保険などの基礎知識
- 実際に起こる事例でケーススタディ
- 4択式テストで理解度をチェック
といった3ステップ構成で、あなたの不安を「自信」に変える実践的な教材です。
もう一人で不安にならなくていい。
あなたの「フリーランスとしての信用」をしっかり支えてくれる教科書です。
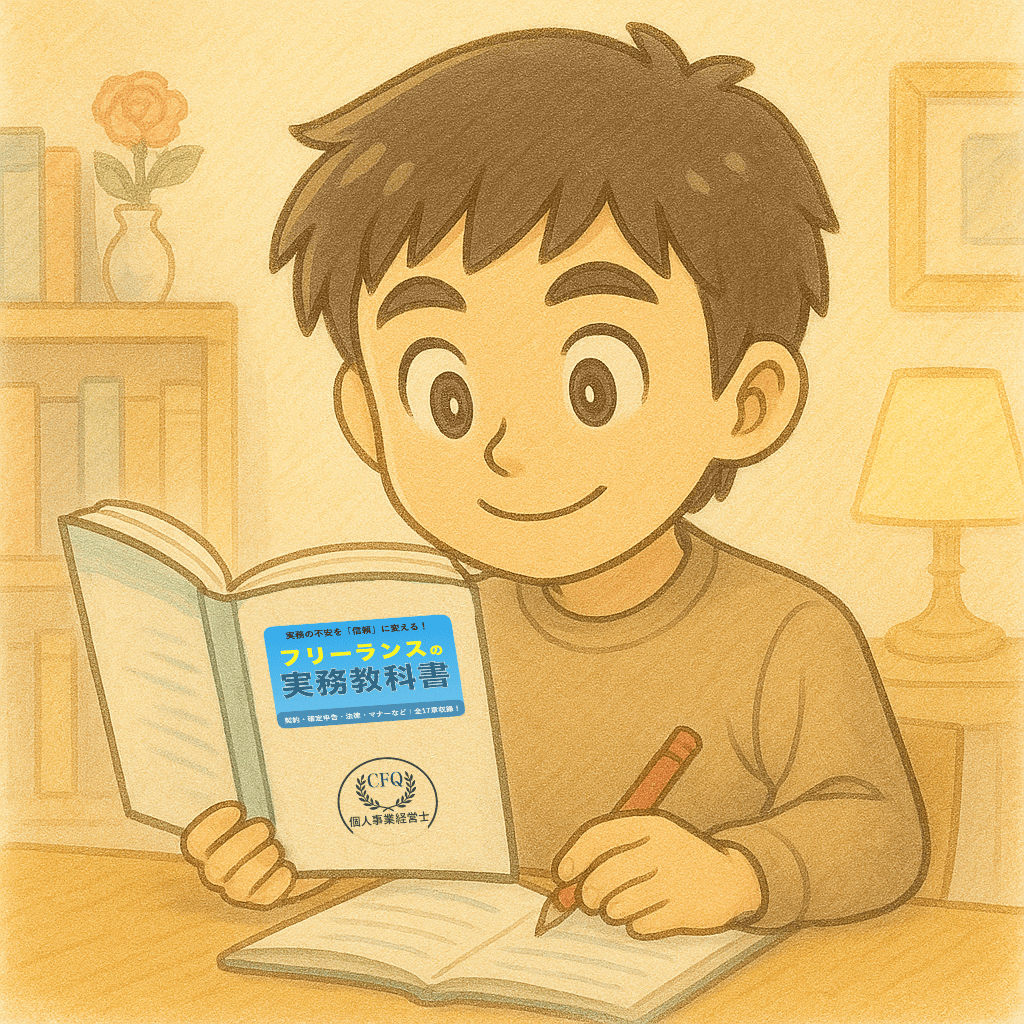
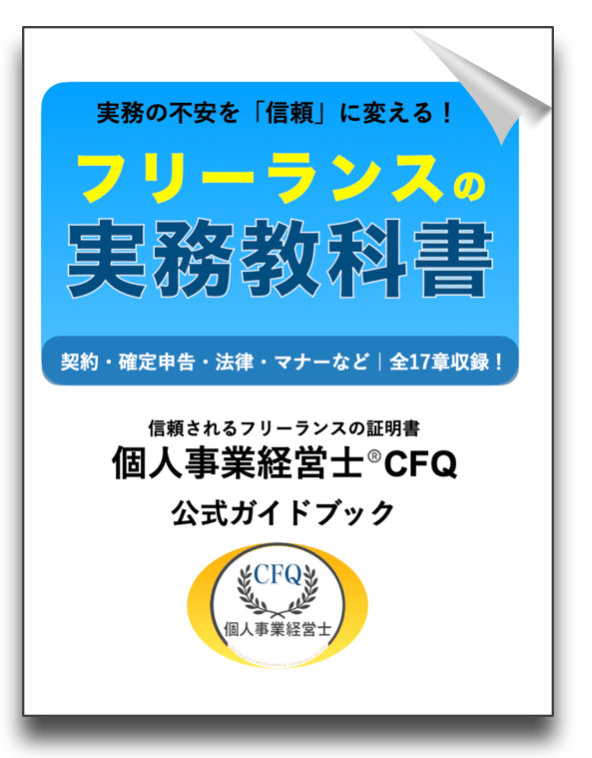
【まとめ】
あの日、減額通告を受けて何も言えなかった自分を、私は今でも悔しく思います。
でも、その経験があったからこそ、今は「黙らない」選択ができるようになりました。法律を知り、相談窓口を知り、自分を守る方法を学んだからです。
フリーランスとして働くことは、自由である反面、すべてを自分で守らなければいけない厳しさもあります。でも、それは決して一人で抱え込む必要はないんです。
法律はあなたの味方です。相談窓口はあなたの支えです。そして何より、あなた自身が自分の価値を信じることが、一番の武器になります。
クライアントから一方的な減額通告を受けたとき、まず深呼吸してください。そして思い出してください。あなたには「NO」と言う権利があることを。
その一歩が、あなたの未来の収入を守り、フリーランスとしてのキャリアをより強固なものにしてくれるはずです。
迷ったときは、一人で悩まずに相談してみてください。きっと、新しい道が見えてきますから。
私自身、いろいろな失敗した経験があったからこそ、今は慎重に、でも自信を持って実務を進められるようになりました。
「税務が不安…」「契約が苦手…」
そんな悩みも、正しい知識を持つことで大きな武器に変わります。
不安をそのままにするのではなく、学んで備えれば、あなたの自信につながり、その自信が信頼を生むという未来が待っています。
フリーランスの新しい資格「CFQ」は、そんなあなたの実務力を一緒に育てていきます。

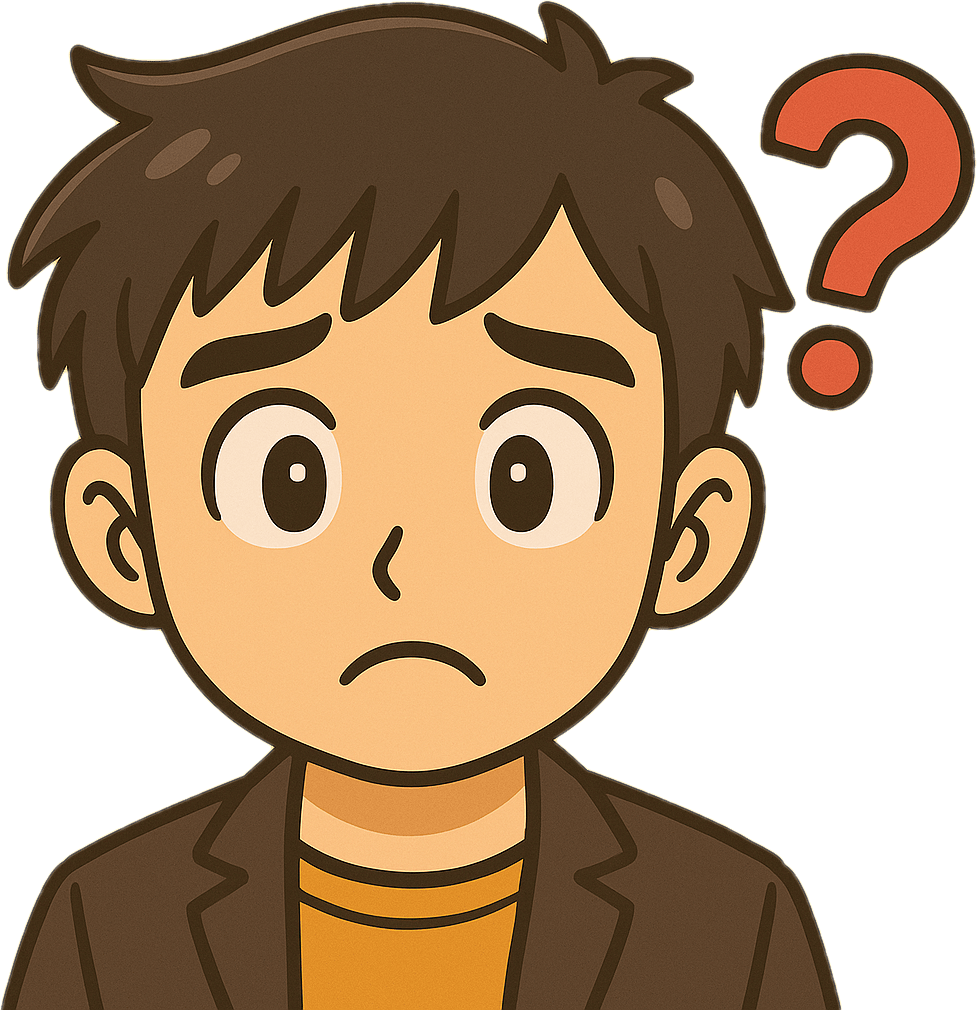 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A) そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!
そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!