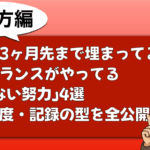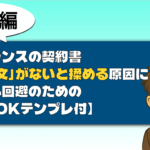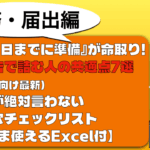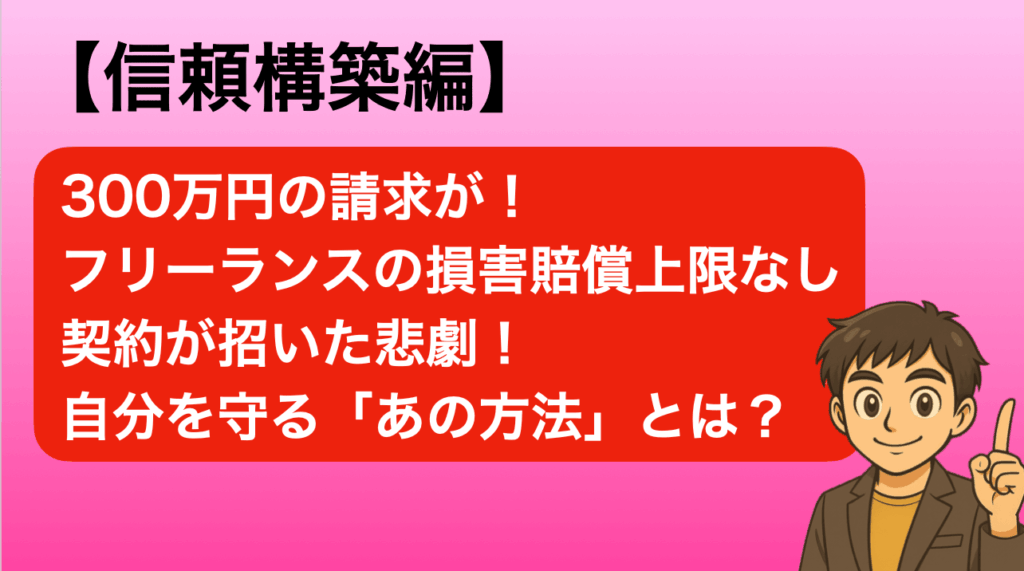
こんにちは。フリーランスひかるです。
先月、私のもとに一通のメールが届きました。件名には「損害賠償のご請求について」の文字。心臓が止まるかと思いました。クライアントのサイトに私が納品したコードが原因で、一時的にシステムが停止したというのです。請求額は300万円。貯金を全部かき集めても足りない金額でした。
あの夜、眠れずに契約書を何度も読み返しました。「損害賠償の上限って、どこにも書いてない…」そう気づいた瞬間、背筋が凍りました。もしかして、この金額を全額払わなきゃいけないの?フリーランスとして5年やってきて、初めて「契約書をちゃんと理解していなかった自分」に直面したんです。
結果的には、弁護士に相談して上限を交渉できました。でも、あの恐怖は今でも忘れられません。もっと早く知っておけば、あんなに怖い思いをしなくて済んだのに。
✅ この記事はこんな方におすすめ
- クライアントとの契約書に損害賠償条項があるけど、内容がよくわからない方
- 万が一のトラブルに備えて、自分の資産を守りたいフリーランス
- 損害賠償保険に入るべきか迷っている方
- 契約書に「損害賠償の上限」を設定したいけど、どう交渉すればいいかわからない方
- クライアントから高額な賠償請求をされて不安を感じている方
フリーランスが直面する損害賠償リスクの現実
フリーランスとして働いていると、「自分は小さな個人事業主だから、大きなトラブルには巻き込まれない」と思いがちです。
私もそうでした。
でも、実際には業種を問わず、多くのフリーランスが損害賠償のリスクと隣り合わせで仕事をしています。
どんなときに損害賠償が発生するの?
エンジニアなら、納品したシステムのバグでクライアントのビジネスが止まってしまったとき。
デザイナーなら、著作権侵害のある素材を使ってしまい、クライアントが訴えられたとき。
ライターなら、事実誤認の記事を書いてしまい、クライアントの信用が傷ついたとき。
コンサルタントなら、誤ったアドバイスでクライアントに経済的損失を与えたとき。
2023年には、あるフリーランスのWebデザイナーが、納品したECサイトのセキュリティ不備により個人情報が流出し、クライアントから約500万円の損害賠償を請求された事例が報道されました。
結局、裁判で200万円の支払いが確定したそうです。
この金額、個人で支払うには相当重いですよね。
私の場合も、システム停止によってクライアントの営業機会が失われたという理由で請求されました。
「たった数時間の停止なのに、なんでこんな金額に?」と思いましたが、クライアント側には売上予測や機会損失の計算根拠があったんです。
契約書に何も書いてないと、どうなる?
ここが一番怖いところです。
契約書に損害賠償の上限が明記されていない場合、民法の原則では「発生した損害の全額」を賠償する義務が生じます。
つまり、理論上は青天井なんです。
私が震えたのは、まさにこの点でした。
契約書には「瑕疵があった場合は賠償責任を負う」とだけ書いてあって、上限額の記載がなかったんです。
300万円の請求も、法的には妥当性があるかもしれない。
弁護士にそう言われたとき、本当に目の前が真っ暗になりました。
フリーランス向けの法律相談を行っている「フリーランス・トラブル110番」 によると、相談件数の約15%が損害賠償に関するものだそうです。
決して珍しいトラブルではないんですね。
損害賠償の「上限設定」がフリーランスを守る理由
あの恐怖を経験してから、私は契約書の見方が180度変わりました。
特に重要なのが「損害賠償の上限」を設定すること。これは、フリーランスにとって命綱のようなものです。
上限設定の実例と相場感
一般的なフリーランス契約では、損害賠償の上限を「契約金額の100%」または「直近3ヶ月分の報酬合計額」に設定することが多いです。
例えば、月50万円のプロジェクトなら、上限も50万円。
これなら、万が一のときも支払える範囲内に収まります。
私が弁護士と一緒に作り直した契約書には、こう書きました。
「本契約に起因して生じた損害賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、上限を本契約の報酬総額(消費税込)とする」。
この一文があるだけで、心の安定感が全然違います。
大手企業との契約では、上限を「年間契約金額の50%」に設定している例もあります。
一方、システム開発など高額プロジェクトでは、上限を1,000万円や2,000万円と具体的な金額で定めることもあるようです。
ただし、私のような小規模フリーランスの場合、支払い能力を考えると契約金額の範囲内が現実的でしょう。
上限があっても例外はある
注意したいのは、すべてのケースで上限が適用されるわけではないこと。
故意または重過失による損害、秘密保持義務違反、著作権侵害などは、上限の対象外とされることが多いです。
つまり、上限設定は「うっかりミス」や「技術的な予測不能なトラブル」を守ってくれるもの。
意図的な不正や、明らかな注意義務違反は守ってくれません。
だからこそ、日々の業務で誠実に、丁寧に仕事をすることが大前提なんです。
契約書に上限を盛り込む具体的な交渉術
「でも、クライアントに『損害賠償の上限をつけてください』なんて言ったら、警戒されるんじゃ…?」私も最初はそう思っていました。
でも、実際に交渉してみると、意外とスムーズに進んだんです。
タイミングが命、契約前に動く
一番大切なのは、契約を結ぶ前に話すこと。
すでに仕事が始まっている状態で「やっぱり上限をつけたいです」と言うのは、相当ハードルが高いです。
見積もりや契約書のドラフトが出てきた段階で、自然に提案しましょう。
私が使ったフレーズは、こうです。「今回のプロジェクト、とても楽しみにしています。
ただ、お互いに安心して進めるために、契約書に損害賠償の上限を設定させていただけないでしょうか。
一般的には契約金額と同額程度が相場だと聞いています」。
この言い方のポイントは「お互いに安心」という部分。
クライアントにとっても、明確な上限があることで予算管理しやすくなるというメリットがあるんです。
決して、こちらだけが得する提案ではないと伝えることが大切です。
雛形を用意しておくとスムーズ
実は、多くのクライアントは契約書のひな形を持っていますが、損害賠償条項が不十分なケースが少なくありません。
そんなとき、こちらから具体的な条文案を提示できると、交渉がグッと楽になります。
弁護士ドットコムの「クラウドサイン」 では、フリーランス向けの契約書テンプレートが無料で公開されています。
こうした資料を参考に、自分なりの条文案を準備しておくと良いでしょう。
私の場合、弁護士に5万円ほど払って契約書ひな形を作ってもらいました。
初期投資としては痛かったけれど、その後すべてのクライアントとの交渉で使えているので、結果的にはコスパが良かったです。
断られたときの対応策
正直に言うと、すべてのクライアントが快く受け入れてくれるわけではありません。
特に大手企業は「ウチのフォーマットで」と譲らないこともあります。
そんなときは、次の手を考えます。一つは、後述する損害賠償保険に加入すること。
もう一つは、プロジェクトのリスクを減らすための対策を提案すること。
例えば、テスト期間を長めに取る、成果物のレビュー体制を強化する、など。
それでもどうしても不安なら、その案件は受けない勇気も必要です。
私も一度、上限設定を拒否され、さらに「すべての間接損害も含む」という条項があった案件を断りました。
報酬は魅力的でしたが、リスクとのバランスを考えると、受けない判断が正しかったと今でも思っています。
損害賠償保険という「もう一つの守り」
契約書の上限設定と並んで大切なのが、損害賠償保険への加入です。
私も、このトラブルをきっかけに加入を決めました。
フリーランス向け賠償保険の種類と選び方
フリーランス向けの損害賠償保険には、大きく分けて二つのタイプがあります。
一つは「業務過誤賠償責任保険」、もう一つは「個人賠償責任保険」です。
業務過誤賠償責任保険は、仕事上のミスで発生した損害を補償してくれます。
IT業界なら「IT業務過誤賠償責任保険」、士業なら「専門家賠償責任保険」といった具合に、業種ごとに専門的な商品があります。
私が加入したのは、フリーランス協会が提供する「フリーランス向け賠償責任保険」です。
年会費1万円で、最大5,000万円までの賠償責任を補償してくれます。
さらに、弁護士への無料相談もついていて、あのとき本当に助けられました。
他にも、三井住友海上の「ビジネスフリーランス保険」や、損保ジャパンの「フリーランス総合保険」など、選択肢はいくつかあります。
保険料は年間1万円〜3万円程度が相場。
月額に換算すると1,000円〜2,500円なので、万が一の安心料としては決して高くないと思います。
保険でカバーされないケース
ただし、保険にも限界があります。
故意や重過失による損害、契約違反、知的財産権侵害などは補償対象外になることが多いです。
また、保険金の上限を超える損害は、やはり自己負担になります。
だからこそ、保険だけに頼るのではなく、契約書での上限設定と組み合わせることが重要なんです。
契約書で上限を決めておき、その範囲内を保険でカバーする。
この二重の守りがあって、初めて安心して仕事ができます。
あのトラブルの後、私は保険に入っていたおかげで弁護士費用の一部を補償してもらえました。
精神的にも経済的にも、本当に救われました。
月々のコーヒー代を少し削るだけで加入できる安心感、ぜひ検討してみてください。
今日からできる!フリーランスの損害賠償対策アクションプラン
ここまで読んで、「やばい、自分も何か対策しなきゃ」と思った方、その気持ちを忘れないうちに行動に移しましょう。
明日やろうと思うと、結局やらないまま時が過ぎてしまいます。
私がそうでした。
ステップ1:手持ちの契約書をチェック(今日中)
まずは、今進行中のプロジェクトや、直近で結んだ契約書を引っ張り出してください。
損害賠償に関する条項を探して、以下をチェックしましょう。
- 損害賠償条項はありますか?
- 上限金額は書いてありますか?
- 「一切の損害」「間接損害を含む」といった危険なワードはありませんか?
- 自分が支払える範囲の金額ですか?
もし上限がなかったり、不安な内容だったりしたら、メモしておいてください。
次回の契約更新時に交渉するための材料になります。
ステップ2:自分用の契約書ひな形を作る(1週間以内)
次に、今後使える契約書のひな形を準備しましょう。弁護士に依頼するのが確実ですが、費用が気になる方は、まず無料テンプレートを参考にしても構いません。
重要な条項として盛り込みたいのは、こんな内容です。
- 損害賠償の範囲(直接損害に限定)
- 上限金額(契約金額の100%など)
- 免責事項(不可抗力、クライアント側の原因など)
- 通知義務(トラブル発生時の連絡方法)
自分の業種に合わせてカスタマイズするのがポイント。
エンジニアならバグの定義、デザイナーなら修正回数の上限など、業務特性に応じた条項も加えると良いでしょう。
ステップ3:保険を比較検討する(2週間以内)
並行して、損害賠償保険の情報を集めましょう。
先ほど紹介したフリーランス協会の保険は、加入のハードルが低くておすすめです。
まずは資料請求から始めてみてください。
比較するポイントは、保険料、補償金額、補償範囲、付帯サービス(弁護士相談など)の4つ。自分の年収や案件規模に合った保険を選びましょう。
年収500万円以下なら、補償上限3,000万円〜5,000万円の商品で十分かと思います。
ステップ4:次の契約から実践する
準備が整ったら、次の新規案件から実践です。
見積もりを出す段階で「契約書はこちらのひな形で進めさせていただけますか?」と提案してみましょう。
最初は緊張すると思います。私も声が震えました。
でも、プロとして自分を守るための当然の権利です。
堂々と、でも丁寧に伝えれば、ほとんどのクライアントは理解してくれるはずです。
もし断られても、落ち込まないでください。
その経験を次に活かせばいいだけです。
私も何度か断られましたが、その度に説明の仕方を改善して、今では8割以上のクライアントに受け入れてもらえています。
 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A)
Q1. フリーランスの損害賠償額は、最大でどれくらいになる可能性がありますか?
A:👉契約書に上限が明記されていない場合、理論上は発生した損害の全額が対象になります。実際の裁判例では、数百万円から数千万円の判決も出ています。IT業界では、システム障害による機会損失が高額になりやすく、1,000万円を超えるケースもあります。だからこそ、契約段階で上限を設定しておくことが重要なんです。
Q2. 個人事業主のフリーランスでも、損害賠償保険に入れますか?
A:👉はい、入れます。むしろ、法人化していない個人事業主こそ加入すべきです。個人事業主の場合、事業の負債は個人資産にも及ぶため、保険でリスクをカバーする必要性が高いです。年会費1万円程度から加入できる商品も多いので、まずは資料請求してみることをおすすめします。
Q3. フリーランスが契約書で損害賠償の上限を設定すると、クライアントに不信感を持たれませんか?
A:👉適切に説明すれば、不信感を持たれることはほとんどありません。「お互いにリスクを明確にして、安心して長期的に協力できる関係を作りたい」という姿勢で伝えましょう。実際、リスク管理がしっかりしているフリーランスは、クライアントから信頼されやすいです。むしろ、何も確認せずに契約する方が、プロとして不安に思われるかもしれません。
Q4. すでに進行中のプロジェクトで、損害賠償条項がない契約書を交わしてしまいました。今から追加できますか?
A:👉双方の合意があれば、契約の途中でも変更は可能です。ただし、実務上は難しいケースが多いのが現実です。もし交渉が難しそうなら、せめて損害賠償保険に加入して、自分でリスクをカバーしましょう。そして、次回の契約更新時に必ず条項を追加するようにしてください。今回の経験を教訓にして、今後の契約では確実に盛り込むようにしましょう。
Q5. フリーランスとして小さな案件しか受けていないのですが、それでも損害賠償対策は必要ですか?
A:👉案件の大小に関わらず、対策は必要です。月10万円の案件でも、ミスによる損害が数百万円に膨らむ可能性はあります。特にデータ流出や著作権侵害など、影響範囲が広いトラブルは金額が読めません。小規模だからこそ、一度の賠償請求で事業継続が困難になるリスクがあります。最低限、保険への加入だけでも検討してください。
 そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!
そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!
フリーランスの実務や疑問を解決するためには、「フリーランスの実務教科書」をお勧めします。
この参考書は、単なる理論の解説ではありません。
- 届出・税務・契約・保険などの基礎知識
- 実際に起こる事例でケーススタディ
- 4択式テストで理解度をチェック
といった3ステップ構成で、あなたの不安を「自信」に変える実践的な教材です。
もう一人で不安にならなくていい。
あなたの「フリーランスとしての信用」をしっかり支えてくれる教科書です。
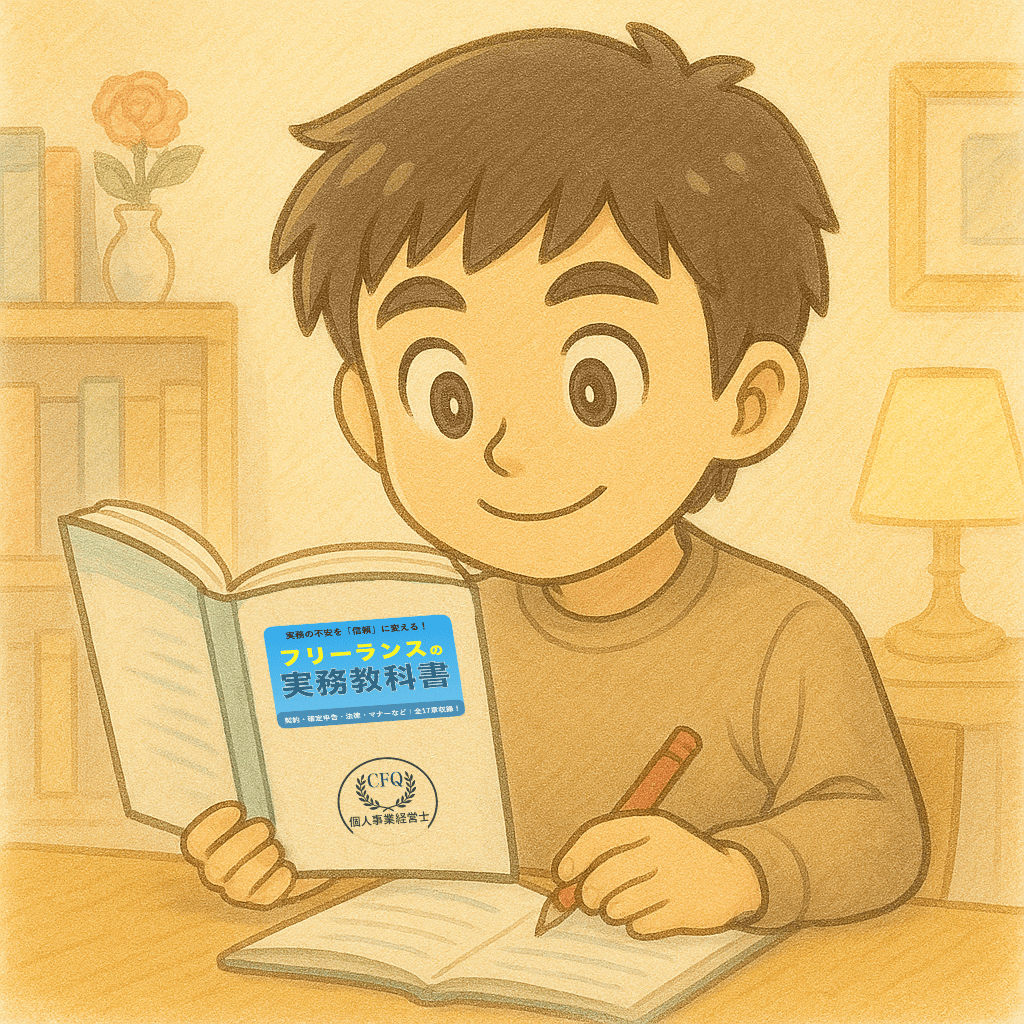
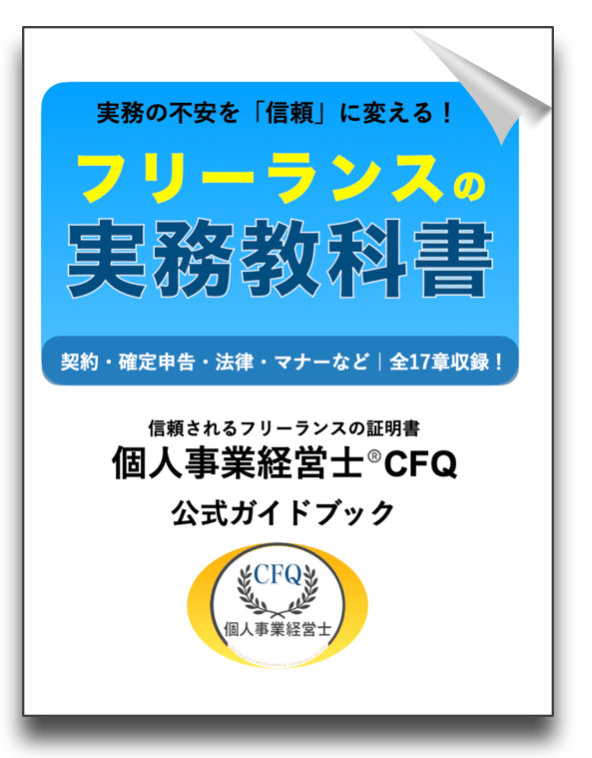
【まとめ】自分を守る知識は、最高の投資
あの300万円の請求メールを受け取った日から、私のフリーランス人生は変わりました。怖かった。本当に怖かった。でも、その恐怖が私に大切なことを教えてくれたんです。
フリーランスとして自由に働けるのは、本当に素晴らしいことです。好きな場所で、好きな時間に、好きな仕事ができる。でも、その自由と引き換えに、リスクも自分で背負わなければいけません。
契約書の損害賠償条項に上限を設定すること。保険に加入すること。たったこれだけで、あなたの心は驚くほど軽くなります。夜、安心して眠れるようになります。クライアントとの関係も、対等で健全なものになっていきます。
今日、この記事を読んでくれたあなたは、もう何をすべきか知っています。あとは行動するだけ。最初の一歩は小さくて構いません。まずは手持ちの契約書を開いてみる。それだけでも、十分なスタートです。
自分を守る知識は、誰にも奪われない財産です。スキルや実績も大切ですが、長くフリーランスとして活躍するためには、こうした「守りの知識」も同じくらい重要なんです。
あなたのフリーランスライフが、もっと安心で、もっと自信に満ちたものになりますように。一緒に、賢く、したたかに、でも誠実に、この道を歩んでいきましょう。
「税務が不安…」「契約が苦手…」
そんな悩みも、正しい知識を持つことで大きな武器に変わります。
不安をそのままにするのではなく、学んで備えれば、あなたの自信につながり、その自信が信頼を生むという未来が待っています。
フリーランスの新しい資格「CFQ」は、そんなあなたの実務力を一緒に育てていきます。

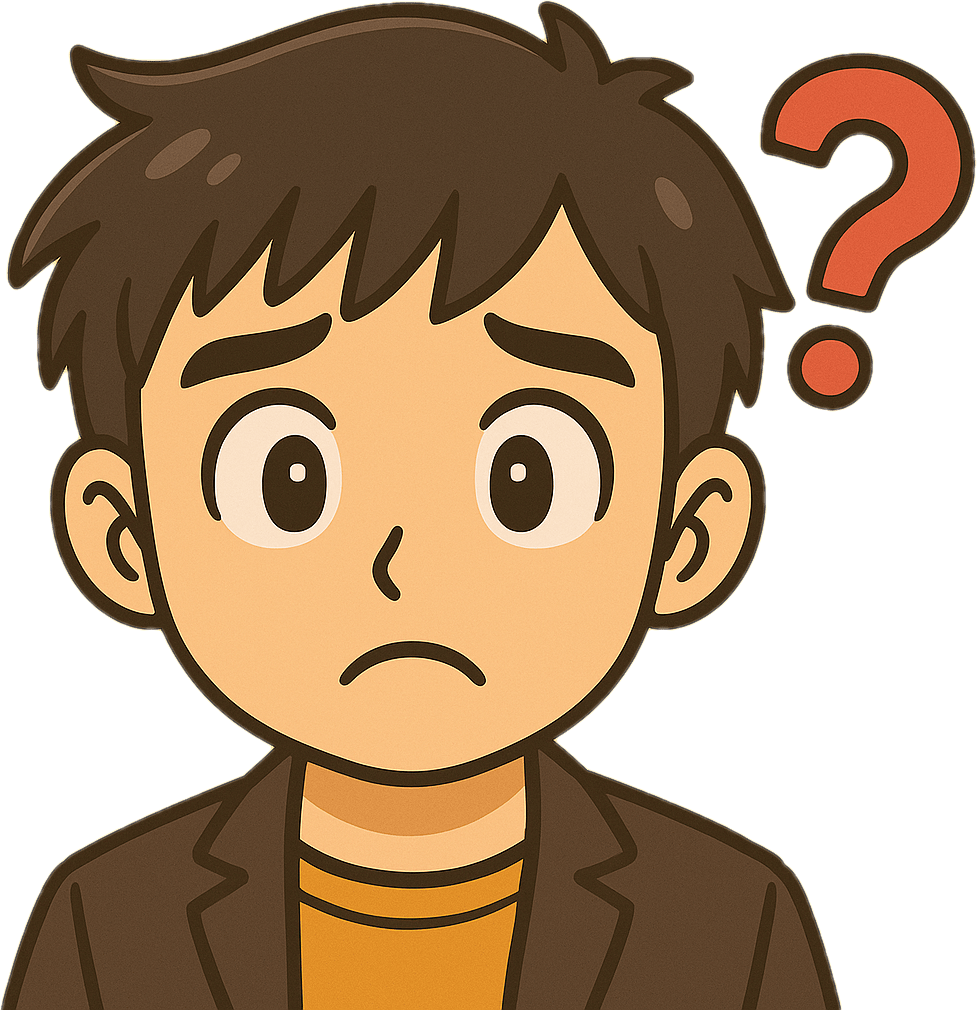 よくある疑問と誤解(Q&A)
よくある疑問と誤解(Q&A) そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!
そんな「フリーランスの実務不安」この1冊が解決!